色違いのロゼリア大騒動!
第1話 第2話 第3話 第4話 第5話
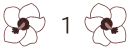 その年のバレンタインデーに、カイとハウはガラル地方のシュートシティを訪れていた。
その年のバレンタインデーに、カイとハウはガラル地方のシュートシティを訪れていた。
「バトルタワー楽しかったねー。アローラのバトルツリーとはまた違ってさー。」
バトルタワーでのポケモンバトルを終えて、2人は街を歩いていた。故郷では目にしないポケモンたちを間近で見られて、ハウはとても満足そうだった。パルスワンの素早い動きは本物の稲妻のようだったとか、キョダイマックスリザードンの迫力は圧倒的で、炎の翼が特にかっこ良かったとか、ハウの多弁はとどまるところを知らない。
「でもおれ実は、ダイマックスさせるのまだ慣れないんだー。ポケモンあんなに大きくなっちゃうでしょ。おれの気持ち届いてるかなって、ちょっと心配でー。」
眉を下げて苦笑するハウ。確かに彼はポケモンをダイマックスさせる時、妙に緊張した面持ちだった。そんなふうに感じていたのか。カイはふふっと微笑むと、ハウの手を握った。
「大丈夫ですよ、ハウさん。ダイマックスポケモンにもハウさんの気持ち、ちゃんと届いてると思う。もしそれでも不安なら……次は私と一緒に投げよう、ダイマックスボール。」
カイの提案に、ハウは笑顔をぱっと咲かせた。
「それめっちゃいいねー。カイと一緒なら、絶対大丈夫な気がするー!」
ハウが意気揚々と右手を掲げた時だった。その手首に付けっぱなしになっているバンドを見つけて、カイもハウも同時にあっと声を上げた。
「ダイマックスバンド、借りたまま来ちゃった!」
ありゃーと頭をかいた後、まあいっかーとハウは口調を明るく切り替えた。
「レンタルポケモンたちを返す時に、一緒に返せばいいよねー。一応カシダさんに連絡しとくよ。」
そう言ってハウは、スマホロトムを取りだす。
じつは今カイとハウは、バトルタワーのレンタルポケモンたちが入ったボールを3個預かっていた。
バトルタワーでは、誰でも気軽にバトルに参加できるよう、貸し出し用の備品やポケモンが用意されている。ハウはバトルタワーデザインのダイマックスバンドがお気に入りで、いつも好んで借りていた。今日はたまたまバンドだけでなく、ポケモンもレンタルして連戦を楽しんでいたのだが、指示を出し、技の成功を褒め、勝利の味を分かち合っているうちに、レンタルポケモンたちはすっかりカイとハウに心を開いていた。特にゴリランダー、エースバーン、インテレオンの3体が2人にべったり懐いてしまい、バトルを終えてポケモンを返そうとした時も、レンタル担当のカシダ氏が驚くほどしょんぼりと悲しげな様子を見せた。それでカイとハウはカシダ氏から、彼らを連れて散歩をしてきてくれないかと頼まれたのだった。
「この子らもバトルタワーの景色ばっかりじゃ飽きてしまうだろうから。どうだろう、お願いできるかな?」
もとよりカイとハウはバトルタワーを楽しんだ後、バレンタインディナーのために予約したレストランの入店時刻まで、シュートシティ内を観光する予定だった。旅路はにぎやかなほうがいい。カイとハウはカシダ氏の依頼を快く受け入れた。
「そろそろゴリランダーたちと一緒に歩こうか。」
ハウが連絡を終えたのを見計らってカイが言うと、ハウはもちろん賛成してくれた。
かちりとスイッチを押してボールを開放すると、光の中に3体が躍り出た。
ゴリランダーが上げた吠え声の意味は、ポケモンの言葉が分からなくたってすぐに知れる。やったあ、待ってました! とその輝く表情に書かれていたからだ。
エースバーンはひときわ高く鳴いたとたん、豪速で道の向こうまで駆けて行ってしまった。カイが慌てて「エースバーン!」と呼ぶと、同じ速度で戻ってきて、嬉しそうにカイとハウの間でぴょんぴょん跳ねた。
インテレオンは最も紳士的な様子で静かにたたずんでいたが、実はそわそわと辺りを観察しており、その視線に合わせてしっぽの先がぴこぴこ動いているのが、カイの位置からはバレバレだった。
カイとハウが3体それぞれを軽くなでてやると、ポケモンたちはめいめいに喜んで体を揺らした。みんな真面目でバトルも強い、とってもいい子たちだ。
「よーし、それじゃあシュートシティ散策に、レッツゴー!」
ハウが天高く突きだした拳に、カイとゴリランダーは同じように片手を上げて「おー!」と続き、エースバーンは両手の突き上げとその場の跳躍で答えた。インテレオンは手を上げはしなかったけれど、すました顔でさっさと歩き始めたので、もしかしたら心中では誰よりも一番お散歩を楽しみにしていたのかもしれない。
待ってよーインテレオン、と声をかけながら、カイとハウとポケモンたちは、シュートシティの街並みに繰りだした。
ガラルの首都は華やかだ。あらためてそう思ったのは、街中が花の香りに満ちているからだった。普段でもシュートシティには、スタジアムの前や川沿いの道に出店の類いが連なっているが、今日は特に花屋が多い気がした。スコーン屋とかアクセサリー屋まで、店頭に販売用のバラを並べている。
花の香りは草タイプのポケモンを誘うのだろう。野生なのか近くにトレーナーがいるのか、スボミーやヒメンカがふわふわと楽しげに辺りを歩いていた。
ゴリランダーも例にもれず、立ち止まって大きな花バケツに顔を近づけ、くんくんとにおいをかいでいた。バケツには、紫の小さな花がぶどうのようにしだれて咲くライラックの束が入っていた。
「その花が好きなの?」
カイが尋ねると、ゴリランダーは遠慮がちに目を細めた。すると、ハウがさりげなく出店の店員に声をかけ、ライラック1枝分の金額を支払うと、カイにウィンクした。カイは目線で礼を返し、一番きれいなライラックを1本選び取って、ゴリランダーの頭に飾ってやった。彼の大樹にも似た深緑と黒檀色の体毛の上で、ライラックの紫がしっとりと揺れた。
「うん、すごくよく似合ってるよ、ゴリランダー。」
ゴリランダーは少しの間、目をぱちくりさせてカイとハウを見つめるばかりだったが、やがて出店に置いてあった鏡に自分の姿を映すと、ぱあっと大きく口を開けた。喜びに2、3度胸をたたくと、ウォーと声を上げながら道を駆ける。どうやら先を行くエースバーンに自慢したかったようだ。
誇らしげにライラックを見せるゴリランダーと、ゴリランダーの話を聞いて跳ねるエースバーン。インテレオンは彼らのやり取りを1歩離れた所で観察している。
カイとハウはそんなポケモンたちの様子を、にこにこと一緒に見守った。
「なーなーカイー。あそこなんだかすごそうだよ。行ってみよー!」
そんなふうにみんなで歩いている途中、ハウが指したのは1軒の花屋だった。出店ではなく、通常もそれを生業としている戸建ての店舗だ。ふわんと良い香りが漂い、店の前にいくつも花バケツが置かれているのは他と同じだが、変わっているのはそのバケツの中身だった。咲き誇る花の色は、赤、白、黄などの見慣れたものに加え、ウルトラマリンブルー、緑と橙のバイカラー、漆黒、さらには虹色まであった。染色花だ。
鮮やかな色彩の花の側には、おそらく花屋のポケモンなのだろうロゼリアが何体かいて、道行く人々を甘い香りで呼びこんでいた。
「カイ、見てー。このバラ虹色だー。どうやってこんなの作るんだろうー?」
7色のバラをしげしげと眺めながら、ハウがそう言った時だった。
「それはね、茎を何本かに裂いて、染色液を吸わせるとできるのよ。」
店の奥から、長い亜麻色の髪を後ろで束ねた壮年の女性が現れて、ハウの質問に答えた。きっとこの花屋の店主だろう。ロゼリアたちがぴょこぴょこと足元にすり寄っていた。
「いらっしゃいませ。おしゃれなゴリランダーを連れたトレーナーさんたち。何かお探しの花がありますか?」
名前を呼ばれて、ゴリランダーはライラックの花かんざしを揺らす。
「えっと、花を探しに来たってわけじゃないんだけどー。」
ちょっぴり気まずそうに、ハウはみんなで散歩をしていたこと、たまたまこの店の染色花に目が留まって思わず立ち寄ったことを話した。
「真っ黒や虹色の花が、目立って見えて。今日はどこでも花を売ってるから、余計にさー。」
「ああ、今日はバレンタインデーだからね。ガラルではバレンタインデーに、愛する人へバラの花を贈ることが多いのよ。」
なるほど、それで街中に甘い香りが満ちていたというわけか。
と、カイたちが感心したところで、花屋に1組の若い男女がやって来た。お客さんだ。店主が彼らの対応を始めたので、カイたちは邪魔にならないよういったん店を離れることにした。
店の外で迎えてくれたのは、エースバーンだった。一緒にいたと思ったのに、いつの間に外に出ていたのだろう? と疑問が言葉になるよりも先に目についたのは、エースバーンが頭に載せている花冠だった。
「わー、エースバーン、それとっても素敵だねー! どこで見つけたの?」
ハウが尋ねると、エースバーンは手招いた。彼が案内してくれたのは、隣の建物との間にある狭い道だ。
薄暗い路地に面した花屋の勝手口の前に、1人の少年とロゼリアがたたずんでいた。
「ん、なんだよ。お前のご主人にその冠、見せてやれたのか?」
少年はそう尋ねた後、エースバーンが連れてきたカイたちの存在に気が付いた。
亜麻色の髪を短く整えた、まだ10にも満たない子供だった。彼は傍らのロゼリアを少し抱き寄せると、口をきゅっと引き結んで、カイとハウを見つめた。2人がゴリランダーにインテレオンという大きなポケモンを連れていたので、おびえてしまったのかもしれない。
「アローラー。あのー、きみがエースバーンに花冠をくれたの? どうもありがとう。」
なるべく怖がらせないよう、精一杯のやわらかな口調と笑顔で、ハウが話しかけた。少年は少し黙った後、いや、と否定した。
「花冠を作ったのはぼくじゃないよ……。そのエースバーンが、頭に花を乗せてもらいたがってるみたいだったから、ロージィが作ってやったんだ。」
ロージィ? とカイが首を傾げると、少年はロゼリアを2人の前に出して見せた。
「うん。ぼくのロゼリア。ロージィって名前。」
きゅるっとロゼリアが鳴いた。その腕の先に咲いたバラは、普通のロゼリアの赤と青ではなく、紫と黒の色をしていた。
「わー、すげー! 色違いのロゼリア!? おれ初めて見たよー!」
興奮するハウに、少年は得意げな様子で胸を張った。しかし、なでてもいいー? とハウが問うと、だめだめ! とまたロゼリアを抱き寄せて遠ざけてしまった。
「ロゼリアには、そう、毒のとげがあるからな。シロートが触るとけがしちゃうよ。だから、触るのはだめ。」
「そっかー。……あっ、そうだ!」
おれいい物持ってるよー、と言いながらハウが鞄から取り出したのは、光の石だった。ロゼリアを進化させられる、不思議なエネルギーの詰まった石だ。
「これ、きみにあげるー。きみのロージィ、きっとすごくきれいなロズレイドになると思うんだー。エースバーンの花冠のお礼だよー。」
ところが少年は、ハウの手に乗った石を最初は興味深そうにのぞきこんだものの、はっとして慌てたように首を振った。
「い、いらない! 別に、花冠は、店に出せない余った花を使っただけだから。お礼とかいいよ。なあ、ロージィ?」
ロージィは少し首を傾げて、それでも賛同の意を示すように、紫と黒の両花をふるると揺らした。
「それから、ぼくの名前は『きみ』じゃない。ライヤだ。花屋の息子のライヤ。お兄ちゃんたちの名前は?」
半ば話題をそらされたような気もしたが、2人が名乗っていないのは事実だった。ごめんごめんと謝りながら、ハウは改めて笑顔を向けた。
「おれねー、ハウ! アローラから来たんだー。こちらはおれの恋人、カイ!」
ハウの紹介を受け、カイもにっこり笑って会釈した。ああ、とライヤは納得の表情を浮かべた。
「バレンタインの花を買いに来たってことか。」
「うーん、厳密に言うと違うんだけどー。」
「ぼくがいい花、選んでやるよ。来て!」
ライヤはぱっと駆けだすと、カイとハウの側を通り過ぎ、ゴリランダーとインテレオンの間も身軽にすり抜け、「早く来いよ」と振り返ってカイたちを手招いた。ただ、ライヤを追おうとしたロージィに対してだけは、だめ、と同行を許さなかった。
「ロージィはそこで待ってて。」
ロージィは少し寂しそうな顔をしたが、素直に足を止めた。そのやり取りを見ていたカイとハウに、ライヤは気まずそうに口を開く。
「あ、あのさ……ロージィのこと、ママには黙っててほしいんだ。いい?」
黙るとは、ロージィの何についてのことだろう?
事情は分からないが、ライヤがなんだか思い詰めた様子だったから、カイとハウはとりあえずうなずいた。それでライヤは安心したらしく、再び勢いよく駆けだして花屋の中に入っていった。
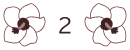 ライヤの母――花屋の店主は、まださっきの男女の対応を続けていた。山のような花の束を抱えて、そこに新たな種類の花を乗せたり、差し色を変更したりしながら、アレンジメントの具合を相談している。かなり豪華な花束ができあがりそうだ。
ライヤの母――花屋の店主は、まださっきの男女の対応を続けていた。山のような花の束を抱えて、そこに新たな種類の花を乗せたり、差し色を変更したりしながら、アレンジメントの具合を相談している。かなり豪華な花束ができあがりそうだ。
「うちの花はすっげーだろ。普通の花だけじゃなくて、ロゼリアの左花みたいに青いバラとか、キレイハナみたいな2色の花だってあるぜ。」
ほら、とライヤが自慢げに黄と緑の2色花のバケツを差し出して見せる。これに大きめの赤い花を2輪合わせたブーケが、キレイハナのトレーナーに大人気なんだと説明してくれた。それから黒い花束は悪タイプのトレーナーとか、ガラル交通に勤めている人への贈り物としてもよく選ばれているそうだ。
「そらとぶタクシーのアーマーガアの、かっこいいつやつやの黒を表現するためには、自然の花色だけじゃ難しいからな。葉っぱとか花びらにきらきらの粉を振ったやつもあるんだぜ。見て!」
もはやカイとハウのためにいい花を選んでくれるというよりも、完全にライヤの好きな花を紹介したいだけだ。とはいえ、一生懸命に花の説明をするライヤの姿は、小さいけれども立派な花屋の店員さんだった。カスミソウを眺めるインテレオンに、色とりどりに染まった他のカスミソウを見せている。エースバーンには花冠と同じ花が入ったバケツを示してやり、ゴリランダーが葉材に興味を持ったので、小さな観葉植物の鉢をいくつか持ってきた。
ポケモンたちに丁寧に話を聞かせるライヤの姿を見て、彼は花とポケモンとこの店が本当に大好きなんだなと、カイは微笑んだ。
「とっておきは、へへへ、驚くなよー。じゃーん! 虹色のバラ! どーだ、すごいだろ!」
ライヤの笑顔は、7色のバラよりもなお輝いて見えた。ハウがにこにことうなずいた。
「うん。おれねー、これ好きだよ。こんなふうに染まるなんて、すごいよねー。」
「あれっ? なーんだ、もう知ってたの。」
「実はさっき店長さんに教えてもらったー。」
花屋の店主は、ちょうど商談をまとめ終えたところだった。豪華な花束を注文してくれた客たちと握手を交わし、二言三言親しげな挨拶をやりとりしながら、店の外まで見送っていた。
見送りが済むと、店主は息子とカイたちの方を向いた。
「ライヤ帰ってたのね。おかえり。ありがとうね、トレーナーさんたち。うちの子に付き合ってもらっちゃって。」
「ぼくがお客さんに花の説明してあげてたんだよう。」
あらあらそれは失礼しました、と店主は慣れた様子だ。
「ところでライヤ、ロージィは? 今朝から会ってないんだけど。」
続いて発された母の言葉に、ライヤはぎくりとして体をこわばらせた。息子のわずかな表情の変化は、母親にはすぐに知れたらしい。
「どうしたの? ロージィに何かあったの?」
少し声音を低くして、彼女は尋ねた。ライヤは答えなかった。困った母親の視線は、カイとハウに向けられた。
あなたたち、ロージィについて何かご存じ?
同時にライヤのすがるような視線も、カイとハウに注がれる。
お願い、ママには何も言わないで。
2つの視線の板挟みになって、さあどうしようかとカイがハウと顔を見合わせた時だった。
「ライヤ!」
甲高い子供の声が店の外で響いた。直後、ばたばたと激しい足音と共に、数人の少年たちが花屋に飛びこんできた。入口近くにいたエースバーンが驚いて場所を空けた。
「ライヤ、大変だ! ロージィがさらわれた!」
少年たちの数は3人。歳はライヤと同じくらいだ。ライヤの学友だろうか。耳を疑うような彼らの知らせに、ライヤはすぐには反応できなかった。
「ロージィが……えっ? なん、だって?」
しかしライヤの問いに答える前に、3人の中で一番背の高い子が、わっと泣きだしてしまった。
「おれが、おれが悪いんだ。ライヤが本当に色違いのロゼリア持ってたから、おれ、うらやましくて、悔しくて、ロージィなんかいなくなっちゃえばいいのにって思っちゃって、それで、あんな怪しいおじさんにロージィのことを教えて……」
その後の言葉は、泣き声に飲みこまれて聞き取れなかった。うわああぁんと涙を流す友人を、1人は背中をたたいて慰め、もう1人は事情の説明を引き継いだ。
「オレたちがポケモンドロボーに、色違いのロゼリアのこと、教えちゃったんだ。それでロージィがさらわれた。ライヤ、ほんっとうにごめん!」
少年たちが、そろってがばりと頭を下げた。花屋の空気は、およそ花など咲きそうにないぐらいの温度に、冷たく凍りついた。
店内に再び芽吹きの風を送ったのは、ライヤの母だった。
「ちょっと待って、どういうこと……? ロージィは普通のロゼリアよ? うちには色違いのポケモンなんていないわ。」
3人の少年たちが、そろってがばりと頭を上げた。誰かが何かを言いだす前に、今度はライヤがわっと泣きだした。
「ごめんなさい! ロージィが色違いのロゼリアっていうのは、うそなんだ。ぼくが、ロージィの花に、染色用のパウダーをかけただけなんだよ。」
間。
それから、「えーっ!!」「うそ!?」「パウダー!?」「ロージィ色違いじゃないの!?」と少年たちは口々に叫んだ。
つまりこういうことらしい。ライヤは友達に色違いのロゼリアを持っていると嘘をついてしまい、後に引けなくなってロージィの花を染めた。友達はロージィが色違いであることを信じたが、嫉妬が高じてポケモン泥棒に色違いのロゼリアのことを教えてしまい、ロージィはさらわれた。
「染色粉の青と黒が急に減ってておかしいなと思ったわ……。」
店主がため息を吐く。
「ごめんなさい……。色水にして吸わせるのは怖かったし、時間もなかったから、そのまま振りかけたら思ったより本物の色違いっぽくなって……。」
ライヤが光の石を受け取らず、母にロージィのことを秘密にしてほしいとカイとハウに頼んだのも、そういう訳だった。進化すればあっという間に色違いのポケモンではないことがばれてしまうし、ライヤと母親の会話から察するに、どうやら内緒で店用の備品を使ったらしい。
ぐすぐすと泣いて謝るライヤの涙は、嘘をついてしまったことと、そのせいでロージィを危険な目に遭わせていることに、とどまるところを知らなかった。
「とにかくこれで、ロージィが色違いのロゼリアだって勘違いしてるのは、ポケモン泥棒さんだけってことだよねー。」
ハウがかがんでライヤの両肩に手を置き、真っ直ぐにその目を見つめた。
「嘘をついたのは良くなかったなー。でもライヤは、色違いになったから、ロージィのことが好きなの?」
「そっ、そんなわけないだろ! ロージィはぼくの家族だぞ! スボミーの時からずっと一緒なんだ。色違いだろうが何だろうが、ロージィがぼくの一番大切なロゼリアだ。ロージィじゃなきゃだめだ。ロージィじゃなきゃ……ロージィ……うっ、うっ、うわああーん!」
再び大泣きしてしまったライヤを、ハウはぎゅっと抱いて頭をなでてやった。
それからハウはカイのほうを見、目線だけで意思を伝えた。
ロージィを、助けにいこう。
カイは力強くうなずいた。カイの隣に立っていたインテレオンも、2人と同じ気持ちを込めた鳴き声を、低く短く発してくれた。
「よく言ったよー、ライヤ。大丈夫、おれたちに任せて。必ずロージィを連れ戻してくるよ。」
涙に濡れたライヤの瞳が、驚きに揺れてハウの顔を見つめた。驚いたのはライヤだけではない。花屋の店主も、3人の少年たちも、目を丸くしてカイたちに視線を注いだ。
はっと冷静になって引き止めようとした店主の言葉を、ゴリランダーが2人に賛同する勇ましい吠え声でさえぎった。
「店長さんは警察に連絡をお願いします。安心してー。なるべく穏便に済ませてくるからー。」
そしてハウは、行こう、とカイの手を取った。インテレオンとゴリランダーが後に続き、エースバーンはもう外に出て豪速で駆けて行ってしまった。カイが慌てて「エースバーン!」と呼ぶと、同じ速度で戻ってきた。
「ロージィをさらった泥棒さん、どっちに向かったか分かるー?」
ハウが3人の少年たちに尋ねると、彼らは異口同音にあっちだよ! と指差した。
「そらとぶタクシーの乗り場の方!」
「きっとタクシーで逃げる気なんだ。」
「髪の毛のないおじさんだったよ。ワルビアルのジャケットを着てた!」
少年たちにありがとう! と礼を言うと、カイとハウとポケモンたちは、花屋を出て道を走り始めた。
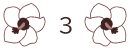 そらとぶタクシーの乗り場に向かって、カイたちはどんどん道を駆けていく。先頭はエースバーン。続いてカイとハウとインテレオン。しんがりはゴリランダーだ。
そらとぶタクシーの乗り場に向かって、カイたちはどんどん道を駆けていく。先頭はエースバーン。続いてカイとハウとインテレオン。しんがりはゴリランダーだ。
ほどなくして、たくさん並んだタクシーのゴンドラと、お行儀良く翼をたたんで待っているアーマーガアたちの群れが見えてきた。その内の1台が、今まさに客を迎えて飛び立つ準備を始めている。ゴンドラに乗り込もうとしているのは、ぴかぴかに剃りあげた頭とワルビアルの描かれた黒いジャケットが目立つ、1人の男だった。腕に何か緑っぽいものを抱えている。
「あの人だ!」
カイが声を上げる。ハウもうなずく。
「もう間に合わない。おれたちもタクシーに乗って追いかけよう!」
ハウがインテレオンをモンスターボールに戻した。カイもゴリランダーを戻し、エースバーンにもボールを向けた。ところがエースバーンは拒否するように、カイに対してかぶりを振った。花冠がその頭上でふわりと揺れる。
カイがエースバーンの意思を図りかねている間に、彼は強く地面を蹴って飛びあがり、一番近くにあった2人乗り用のそらとぶタクシーの上に陣取った。
「どうやらエースバーンは、素敵な花冠をプレゼントしてくれたロージィを、自分の力で助けたいみたいだねー。」
そう言ってからハウは、突然ポケモンが降ってきたので目を白黒させているアーマーガアとタクシードライバーの元へ駆け寄った。
「おれたちのエースバーンがすみません! いきなりだけどー、あのタクシーを追ってー!」
ハウが叫んでいる間に、カイはゴンドラの扉を開けて中に入り込んだ。
「な、なんだあ、あんたら?」
「事情は後で説明するよー! 家族ともいうべきポケモンの命運がかかってるんだ。お願いします!」
タクシードライバーが眉間にしわを寄せてカイとハウをにらんだのは無理もない。けれどもその視線にひるまず、真摯に頼みこんだハウの態度が、思いのほか強くドライバーの心を打ったらしい。
「……よし、わかった。うちのガアが嫌がってねえからな。あんたらを信じよう。乗れ!」
話の分かるドライバーで助かった。ハウが勢いよくカイの隣に座る。ばんっと扉が閉まる音と、アーマーガアの鋭い声が響いた後、ぐんと上から押さえられるような力が体にかかった。
「追い付くためにちょっとスピード上げるぞ! あんたらのウサギちゃんに、振り落とされないよう言っておいてくれ。ゴンドラの屋根にシートベルトを設置するの、忘れちまったからなあ!」
アーマーガアの背中から、ドライバーの声が降ってきた。直後、ゴンドラが大きく揺れる。うわっとバランスを崩したカイの体を、ハウがとっさに抱き支えた。
それからハウは少し身を乗り出し、エースバーン大丈夫ー? と上に向かって呼びかけた。すぐにエースバーンの元気な鳴き声が返ってきた。しっかりつかまっててね! とカイも声をかける。
シュートシティのビルが、広場が、街が、どんどん後ろに流れていく。
「それで? あんたらのご事情、教えてもらえます?」
ドライバーの声は荒かったが、風圧に負けないようにしているだけで、怒っているわけではなさそうだった。それでカイとハウも声を張りあげ、先のタクシーにはシュートシティの花屋さんからロゼリアを奪って逃げているポケモン泥棒が乗っており、自分たちはそれを追っていることを説明する。
「普通のロゼリアなんだけど、ちょっと事情があって花びらを染めちゃってー。色違いのロゼリアだと勘違いされてさらわれちゃったんだ。色違いじゃないと分かれば返してくれると思うからー、とにかく話ができる距離に近づいてほしい!」
ドライバーは少し間を置いて、どう思う? とアーマーガアに問いかけた。アーマーガアは大声で鳴き、ぶんと強く翼を打って加速した。ドライバーはどこか愉快そうに、そうかいとつぶやいた。
「お客さんら、運がいいぜ。ガラル交通トップクラスのベテランコンビのフライトを楽しめるんだからな。大船に乗った気でいな! ま、船じゃなくてタクシーだが!」
がはは、とドライバーの笑い声が風と共に流れていった。なんとか理解してもらえたことに、カイとハウもほっとして頬をゆるめた。
ベテランコンビの操るタクシーは、先を行くタクシーにぐんぐん迫っていった。しかしそう思えた時間は長くなく、縮まっていたはずの両者の距離はやがてぴたりと一定になり、今度は逆に離れ始めた。こちらのアーマーガアが速度を落とした訳ではない。向こうのアーマーガアが、羽ばたきを強めたのだった。
「追われてることに気付いたみたいだねー。」
むーとハウが口をへの字に曲げた。
それから少しの間は、距離が縮まりそうで縮まらない一進一退が続いたが、やがてタクシードライバーのうなり声が聞こえてきた。
「まずいな。やつらシュートシティを出るつもりだ。あの方角はまさか……ヨロイ島か?」
「ヨロイ島ー?」
「そこに逃げこまれたら厄介だ。入るには特別なパスがいる場所でな。なんとか行き先だけでも変えさせないと。」
「よーし分かった! おじさん、少しの時間でいいから、もうちょっとだけあっちのタクシーに近付けるー?」
タクシードライバーの顔はもちろんカイたちには見えなかったが、その時彼がにいっと自信ありげに口角を上げたのが、声音で知れた。
「うちのガアを甘く見てもらっちゃ困るね! 2人用ゴンドラも余裕で運べる、一等大きなアーマーガアだぜ!」
ドライバーの言葉にアーマーガアの鋭いひと声が応じ、タクシーがスピードを上げた。ハウがひゅうと口笛を吹く。
「よーし、エースバーン! 相手のタクシーに向かって、火炎ボールだ! でも当てちゃだめだよ。ヨロイ島に行かないように、アーマーガアを驚かせるだけでいい。できるー!?」
今度はエースバーンが「甘く見てもらっちゃ困るね」と吠える番だった。ゴンドラの屋根の上でタン、タンと軽やかなリズムが刻まれた後、燃える光の線が前方のタクシー目がけて一直線に走った。
突然苦手な炎の弾丸に体の真横を通られたアーマーガアは、とっさに航路を変えた。それでもなお当初の方角を保とうとするそらとぶタクシーのプライドに、エースバーンは連続で繰りだす火炎ボールの追撃で挑む。もちろんハウの指示を守って、ぎりぎりのところで外している。
エースバーンのさらに上方からは、ドライバーが無線機にがなる声が聞こえていた。おそらく、相手のタクシードライバーと話をしているのだろう。しかしこちらを警戒されているのか、一向に説得の気配はない。
そうこうしているうちに、向こうのアーマーガアが高度を落とし始めた。エースバーンのおかげで、ヨロイ島に行くのは諦めたようだ。追随して、こちらのアーマーガアも降りていく。
シュートシティの街並みはとっくに抜けていた。眼下に迫るのは広大な草原……そしてそれよりももっと大きな砂の海だった。吹き荒れる激しい風に空気は黄色くけぶり、先は見通せない。
「ワイルドエリアに着陸するぞ!」
ドライバーの大声が、無線機を離れてカイたちに向けられた時だった。先行するタクシーのゴンドラから、男が飛び降りた。着陸間際とはいえ、とても人間が着地できる高さではない。あっと目を見張った瞬間、閃光が空気を裂いた。モンスターボールの開放光だった。1体のカビゴンが砂地の上に召還され、男はその腹をクッションにして無傷で地面に降り立った。男が抱えている小さな緑色のポケモン――ロージィも無事だ。
男とポケモンたちは、砂嵐の中を駆けだした。輪郭が次第に見えなくなっていく。
「逃げられる! おじさん、早くー!」
「ええい、乗客の安全確保がタク屋の最優先事項なんだがな! 頭打つなよ、お客さん!」
カイとハウは座席の上で歯を食いしばり、ぎゅっと身を縮め、互いをかばい合った。直後どどんっと、そらとぶタクシーではおよそ経験するはずのない豪快な衝撃がゴンドラを震わせる。タクシーが止まった。
「大丈夫、カイ!?」「大丈夫、ハウ!?」
カイとハウは顔を見合わせて、少し微笑み、うなずいた。それからハウはカイの手を握り、ゴンドラの扉を開けた。
エースバーンはゴンドラの屋根から降りて2人を待っていたものの、すっかり疲労しているのは明らかだった。あんな足場の悪い中で技を出し、着地の衝撃にも耐えたのだから当然だ。
「お疲れ様、エースバーン。ありがとー!」
「よくやったよ! しばらく休んでてね。」
2人はそう労い、エースバーンをボールに戻した。
それからカイとハウは砂地を駆けだそうとしたが、その前に1度振り返り、つないでいないほうの手を高く掲げた。
「おじさん、アーマーガア、ありがとう!」
「最高のフライトだったよー!」
誇らしそうに翼を広げたアーマーガアの背中の上で、ドライバーが親指を立てた拳をぐっと突き出しているのが、砂煙の向こうに見えた。
 男に追いつけたのは、あれほどの追走飛行の中でも乗客のダメージを最小限に抑えてくれたアーマーガアとドライバーのテクニックの高さゆえに違いない。あるいは火炎ボールによる翻弄が、相手のゴンドラを揺らしに揺らし、ポケモン泥棒の平衡感覚をすっかり奪い取っていたのかもしれない。
男に追いつけたのは、あれほどの追走飛行の中でも乗客のダメージを最小限に抑えてくれたアーマーガアとドライバーのテクニックの高さゆえに違いない。あるいは火炎ボールによる翻弄が、相手のゴンドラを揺らしに揺らし、ポケモン泥棒の平衡感覚をすっかり奪い取っていたのかもしれない。
とにかくカイとハウはポケモン泥棒を追い詰めた。隠れる場所のない砂塵の窪地の真っ只中で、男は大きな岩を背にし、カイたちをにらみつけている。ロージィは男の腕の中でぐったりしていた。暴れないように眠らされたか、気絶させられたのかもしれない。
「ロージィを……そのロゼリアを返して!」
カイが叫ぶと、
「知らねえなあ。こいつは路地裏に1匹でいた野生のポケモンだ。俺がゲットしたポケモンを、返す義理なんてどこにもないね。」
男は平然とそう言ってのけた。むっとハウが眉をつり上げる。
「嘘つきー。男の子たちから聞きだして、そのロゼリアが人のポケモンだって知ってて連れてきてるでしょー。それに自分でゲットしたなら、そんなに弱ってるポケモン抱えて歩かないはずだよー。その子のモンスターボールはー?」
反論され、男はあからさまにどきりとした。そして、あっさりと逆上し罪を認めた。
「う……うるさいうるさい! 俺にはどうしても色違いのロゼリアが必要なんだ。けど、そんなの簡単に手に入るわけねえだろ。仕方なかったんだよ! 彼女を振り向かせるためには、色違いのロゼリアをプレゼントするしかねえんだ! 俺の人生がかかってるんだよ!」
最後のほうはひっくり返った金切り声になった男の主張を、しかしカイとハウは冷ややかに聞いていた。
「でもー、だからってポケモン泥棒していい理由にはならないでしょー。それにねー、残念だけどそのロゼリア、本当は色違いじゃないよー。」
なに、と手元を確認した男が、いやちゃんと青黒の花じゃねえかと怒号を発する前に、「色違いに見えるように、花用のパウダーで染めてるだけなんだよ」とカイが先手を打って補足した。
大きく開いた男の口は、言葉を失って2回ほどぱくぱくと動いた。やっと飛びだした音は、やけっぱちに引きつっていた。
「そ、そ、そんな子供だましの嘘に引っかかるかよ!」
「いやいやー。だからお兄さんが今、子供だましの嘘に引っかかってるって教えてあげてるんじゃんかー。」
「黙れ黙れ黙れ! とにかく俺は何がなんでもこのロゼリアを連れていくぞ! 誰にも邪魔はさせねえ!」
そうわめいた後、男は黒い石を取り出し、ためらいなくぽんと放り捨てた。石は近くにあった岩の割れ目に転がりこみ、直後、赤い光がほとばしる。さらに男は1個のモンスターボールをその光の中に投入した。
「いっけえぇ、カビゴン!」
光の柱の中で、ボールから解放された影がみるみるうちに膨らんだ。現れたのは、山のような巨体のポケモン――いや、腹の上に木や茂みや花園を生やし、何人の妨害に遭っても動かざる決意を具現したかのようなその体は、もはや山そのものと言って差し支えなかった。
「キョダイマックスカビゴン……!」
カイとハウはその威圧感に思わず1歩後ずさったが、相手のポケモンがダイマックスできるということは、こちらのポケモンもダイマックスできるということだ。
「ハウさん。」
カイは名を呼んで、ダイマックスバンドを着けたハウの右手をきゅっと握った。ハウはカイの目を見て、こわばった面持ちをふっとゆるめた。
「カイと一緒なら、絶対大丈夫だ。」
対抗の意思は固まった。相手に話し合うつもりがないなら仕方ない。こちらもダイマックスポケモンで応戦だ。
ハウはカイとつないだ手をいったんほどくと、右手の中にインテレオンのモンスターボールを握りしめた。ダイマックスバンドからあふれる光を吸って、ボールは赤く輝くダイマックスボールに変化した。ハウはそれを両手で抱え持つと、目を閉じて軽く額を押し当てた。カイはハウの手を包むように自分の手を重ね、ダイマックスボールを共に支えると、ハウと同じように額を当てた。
「お願いインテレオン……おれたちに力を貸して!」
祈るようにハウがつぶやく。
顔を上げて互いを見つめ、カイとハウは呼吸を合わせる。
「「せー、のーっ!!」」
勢いをつけたゼンリョクの下投げで、2人はインテレオンのダイマックスボールを高く放りあげた。空中でボールがはじけ、砂嵐越しでもなお輝きを失わない爆発的な光の中で巨大化しながら、インテレオンが姿を現した。人間1人くらいすっぽり入ってしまいそうな大口から放たれた咆哮は、普段の紳士的で物静かな鳴き声とは違い、空気をつんざく振動となって大地を揺るがした。
「インテレオン!」
叫ぶハウの表情に迷いはなかった。どんなにポケモンが大きくなっても、遠くにいるように見えても、自分の気持ちが必ずインテレオンに届いていることを、彼はもう信じられていた。だって、カイと一緒に思いを込めて、ダイマックスボールを投げたのだから。
「ダイストリーム!」
インテレオンが構えた指先に水泡が集まる。集合した奔流は巨大な水の弾丸となって、そびえる山を撃ち抜いた。衝撃ではじけ飛んだ数多の水玉が、雨となって降り注ぐ。ダイマックスエネルギーが技を通じて大気にも作用するのか、雨はそのまま降り続け、舞い散る砂を落とし、地上のカイたちの肌を打った。
もちろん対峙している男にも、彼が抱えているロージィの両花の上にも、大粒の水滴が注がれる。それはロージィに付いたパウダーを洗い流し、青紫の花びらは真紅に、漆黒の花びらは濃青に変化していく。やがて現れたごく一般的な色のロゼリアを、ポケモン泥棒は呆然と見つめた。
「なん、だ、こりゃあ……!」
彼は青色と黒色になってしたたる雨水が服を染めていくのにも気付かず、カビゴンに指示を与えるのも忘れていた。
だが、カビゴンはなかなか賢いポケモンだった。あるいはそれは、特に意思のない寝相のようなものだったのかもしれない。とにかくカビゴンはトレーナーの指揮を失ってもなお、寝そべった体を揺らして大地を割るような衝撃を起こし、インテレオンに攻撃を仕掛けてきた。
猛攻に耐えるインテレオン。頑張れ! 踏ん張って! と雨にも負けない声を張りあげたカイとハウの応援に、インテレオンは重厚な鳴き声を響かせて答えた。
「よーし、一気に決めようインテレオン! おれたちのゼンリョクの、ダイストリーム!」
ハウの掛け声に合わせ、インテレオンが狙いを定めた。現れた水球は降りしきる雨粒を巻きこみ、先の弾よりも強大な水の槍となって、激しくカビゴンの急所を貫いた。
ずどんと山の崩れるような音がとどろき、赤い光が爆発した。ようやく爆風が収まった時には、元の大きさに戻ったカビゴンが、男の側で目を回していた。
やっと入手した色違いのロゼリアは偽物。切り札になるはずだった砦は戦闘不能。
「くっ……そおぉ!」
ポケモン泥棒にはもはや絶望しか残されていない、かと思われた。
しかしカビゴンをモンスターボールに戻した次の瞬間、男はロージィを投げ捨て、がむしゃらに走り始めていた。
あっ、ロージィ!
この期に及んで逃げるつもりか!
助けなきゃ!
捕まえなきゃ!
とっさのことに渋滞を起こしたカイの思考に、風穴を開けてくれたのはハウの声だった。
「ロージィはおれが! カイはゴリランダーと一緒に泥棒を追いかけてー!」
「わ、わかった!」
そうだ。ゴリランダーなら木の根を操って、走るよりも速く男を確保できる。カイは駆けだしながらモンスターボールをつかみ、思いっきり前方に投げた。
「ゴリランダー、ドラムアタック! ポケモン泥棒を捕まえて!」
ウオォッとうなりながら飛び出したゴリランダーは、空中ですでに切り株ドラムを用意し終えていた。着地するやいなや激しいドラム音が響き渡り、地中から猛スピードで現れた木の根が逃げる男を捉えようとした、まさにその時。男の足がふわりと空中に浮かびあがった。
「ウォーグル、エアスラッシュ!」
上空から降ってきた風の刃が、ゴリランダーの操る木の根をずたずたに裂いた。
男がウォーグルの脚につかまって、空からにやりとカイたちを見下ろしていた。
「はっはー! 俺の手持ちがカビゴンだけだと思ったか! そのロゼリアにもお前らにも、もう用はねえ。あばよ!」
待て! とカイが叫んで待つはずもなく、男とウォーグルはぐんぐん上昇していく。あれではゴリランダーの木の根は届かない。どうしよう、何か手段は、とカイが必死に考えを巡らせた時だった。
黒い影が2つ、ウォーグルよりもはるかに速く上昇すると、鉄色に輝く翼のひと打ちを同時に食らわせ、逃走者をたたき落とした。
「今だお客さん! そいつを捕まえろ!」
それは背中に人を乗せた、2羽のアーマーガアだった。そらとぶタクシーのドライバーたちが、カイに加勢してくれたのだ。
ゴリランダーが気合いに満ちた声を発した。決めるなら今しかない!
「ゴリランダー、ウッドハンマー!」
切り株ドラムがビートを刻む。律動に応じてうごめく根っこは、からまり、合わさり、自身で自身を編みこんで巨大なハンマーを形作った。ゴリランダーがドラム連打のフィニッシュを決めた時、ハンマーは勢いよく振り下ろされ、ウォーグルが再び空に舞いあがろうとする意思にとどめを刺した。
さらに木の根は攻撃を終えた後、ハンマーの形を崩して檻となり、ポケモン泥棒を閉じこめた。
「おおっ、ゴリランダー、ナイス!」
思わずカイが歓喜の声を上げると、ゴリランダーはライラックの花を揺らして振り返り、誇らしげに牙を見せた。
「カイー!」
ハウがカイとゴリランダーに駆け寄った。ハウが腕に抱えたロージィは、すっかり元気を取り戻していた。きっとハウが回復薬を使ってやったのだろう。
カイとハウは急いで根っこの檻に近づく。隙間からのぞくと、ポケモン泥棒はウォーグルと一緒に目を回して伸びていた。
2人の側にゆっくりと降りたったのは、アーマーガアたちだった。大きいほうのアーマーガアに乗ったドライバーが、檻を眺めてカイたちの成功を確認し、親指を立てた拳をぐっと突き出した。
「やったな、お客さんたち!」
カイとハウも、ガラル交通トップクラスのベテランコンビに、同じサムズアップで応えてみせた。
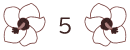 そらとぶタクシーのベテランドライバーは、カイたちを見送った後、ポケモン泥棒を運んだほうの青年ドライバーと合流し、互いの情報を交換した。結果、カイたちのほうが真実だと判断し、助けに入ったということだった。
そらとぶタクシーのベテランドライバーは、カイたちを見送った後、ポケモン泥棒を運んだほうの青年ドライバーと合流し、互いの情報を交換した。結果、カイたちのほうが真実だと判断し、助けに入ったということだった。
青年ドライバーの話によると、ポケモン泥棒は最初、自分のポケモンが病気で、ヨロイ島にいる老師に看てもらわないといけない、と言ってフライトを依頼してきたそうだ。本来はシュートシティ内の移動業務なのでドライバーは悩んだが、急かす男が抱えているぐったりしたロゼリアを見て、とりあえず信用したという。追ってくるカイたちのことも、色違いのロゼリアを狙うポケモン泥棒だと主張する男の言い分に、一度は納得した。しかしよくよく考えてみれば、具合の悪そうなロゼリアをボールに戻す気配もないし、ヨロイ島へのパスを持っているのかという質問の答えも要領を得ず、なんだかおかしいなと思っていたところに、問答無用の飛び降り下車である。本当は彼のほうがポケモン泥棒で、すべては逃げるための行動だったとするほうが、つじつまの合う話だった。
「ごめんよ。知らなかったこととはいえ、泥棒に加担してしまって。」
気まずそうに謝る青年ドライバーに、カイとハウは首を振った。
「ううんー。おれたちも火炎ボール投げちゃったりして、ごめんねー。びっくりしたよねー。」
ハウが青年の相棒アーマーガアをなでてやると、アーマーガアは見た目に反してやわらかな鳴き声で、きゅーと答えた。どうやら許してくれたらしい。
それからカイたちは泥棒を連れ、そらとぶタクシーに乗ってシュートシティへ戻った。警察署にはすでに花屋からの通報が入っていたので、話は比較的早かった。とはいえ、泥棒の引き渡しだとか事情聴取だとかその待ち時間だとかで、かなりの手間を取られてしまった。花屋に連絡してロージィの無事を伝え、ポケモンたちを回復し、待ちきれずに迎えに来てくれたライヤと母に手を振った時も、カイとハウはまだ警察署にいた。
「ロージィ!」
署内でロゼリアと再会したライヤの瞳の輝きは、キバ湖のさざ波を照らす朝日で形容しても足りないだろう。真っ赤に腫れて涙も枯れ果てたかのように見えたライヤの目に、みるみるうちに水が湧きだしてきて、やがて泣き声が爆発した。ぎゅうと抱きしめるライヤの胸に、ロージィも満開の両花を回してしがみついた。ロージィ本来の鮮やかな赤と青の花びらが、ライヤの背中の上で愛らしく揺れていた。
「本当に、本当にありがとう。ロージィを助けてくれて……。ロージィが色違いのポケモンだってうそついて、本当にごめんなさい。」
「もう気にしなくていいよー。ライヤは十分反省したんでしょー。それに、ロージィを助けるために頑張って戦ってくれたのはポケモンたちだからねー。この子たちにも、お礼を言ってあげてー。」
カイとハウはゴリランダー、エースバーン、インテレオンをライヤの前に出してやった。
ライヤは順番に彼らに抱きつき、深い感謝の言葉を繰り返した。ゴリランダーはライラックの花かんざしを揺らしながら、大きな手でライヤの背中をくしゃくしゃとさすってやった。エースバーンはダンスでも踊ると思ったのか、ライヤの両手を握って、その場で一緒にくるくる回った。インテレオンは最も紳士的な様子でライヤの抱擁を受け入れたが、そのしっぽの先がせわしなくぴこぴこ動いているのが、カイの位置からはバレバレだった。
「私からもお礼を言わせてちょうだい。息子の大事なポケモンを……いいえ、私たちの家族を、取り戻してくれてありがとう。」
花屋の店主も、カイたちに向き直り、あらたまって頭を下げた。
「謝礼をしなくちゃいけないわね。何がいいかしら。うちですぐ用意できるものなんて、花束くらいのものだし……。」
「いいっていいってー。とにかくみんな無事だったんだから、お礼なんてそんな気を遣ってもらわなくてもー……あっ。」
言いかけて、ハウがなにかひらめいた顔をした。カイのほうを見て、ちょっと微笑む。
「そういえばおれさー、ガラルのバレンタインのことあんまり知らなくて、今日まだプレゼント用の花束、用意できてないんだよねー。」
花屋の店主がぱっと目を輝かせた。得意な方面で恩義を返せるチャンスに気が付いたようだ。ハウがにっこり笑って、カイに問いかけた。
「カイは、どんな花が好きー?」
尋ねられて、カイもハウの意図を理解した。今回の騒動のお礼として花束を譲ってもらえたら、需給一致の最適解だ。
「全部の花が好き。私のためにハウさんが選んでくれた花なら。」
カイの答えを聞き、あらまあ! と花屋の店主の声が華やいだ。
「奥ゆかしい恋人さんね。それならハウさん、私に任せて。あなたたちにぴったりのお花、お店にたくさんあるから。カイさんのために一番素敵なのを選んであげるといいわ。」
そういうわけで、ハウと花屋の親子とポケモンたちは、そろって花屋に連れだった。警察署での雑事がまだ少し残っていたので、カイがそれを片付けて、後ほどバトルタワー前で落ち合うことになった。
バトルタワーでカイはまず、カシダ氏に事情の報告をした。泥棒の逮捕に協力したポケモンの親トレーナーということで、警察からすでに連絡は入っていたが、ここはきちんと借り主からも説明するのが筋というものだろう。
カシダ氏は思ったよりも寛大に事態を受け入れてくれていた。終わり良ければすべて良し。バトルタワーで形式ばったバトルを繰り返さなければならないポケモンたちに、型にはまらない大冒険を経験させてくれてありがとうと、かえって感謝されたぐらいだった。
「カイー! ごめんね、お待たせー!」
そんなふうにカシダ氏と話をしているうちに、バトルタワーの扉が開く音がして、ハウが入ってきた。ゴリランダーとエースバーンとインテレオンも続く。やあみんなお帰り、ずいぶん楽しい散歩だったんだって? と声をかけるカシダ氏に、彼らはそれぞれに満足げな様子を表明していた。
ハウは後ろ手に何かを隠していた。カイがそれをのぞき見ようとすると、ハウはにこっと笑みを浮かべた。
「それじゃあ、まずはこちらから。みんなに手伝ってもらって、とびっきりのを選んだよー。ハッピーバレンタイン、カイ!」
差し出されたのは、真紅のバラの花束だった。情熱的な色の花が10数本、可愛らしいオーガンジーとリボンに包まれ、カイのためだけに咲き誇っていた。
「わあ、真っ赤でとっても素敵……! ありがとう、ハウさん!」
カイが花束を受け取ると、気品あふれるバラの香りがふわりと空気をくすぐった。と同時に、カイはその花束に小さな封筒がくっついているのに気が付く。開けてもいいかと尋ねると、どうぞとハウは促した。封筒の中には、金の箔押しで縁取られたメッセージカードが1枚入っていた。カイはカードを取り出し、中央に書かれている短い文章に目を通した。
希望、愛情、情熱、真実、
尊敬、栄光、努力、永遠
12の言葉を誓って
きみのアローラより
「これ……『きみのアローラ』っていうのは、ハウさんのことだよね?」
「ば、ばればれでも差出人の名前をあえて書かないのが、ガラル流のバレンタインだって教えてもらったからー。」
やっぱり少しキザな表現だと自分でも思っていたのか、ハウは頬を赤く染めている。
若者たちのやりとりを眺め、カシダ氏も目を細めた。
「12本のバラの花束……ダズンローズか。バラの1本1本に意味を込めた、ガラルのバレンタインでは王道の贈り物だ。いいものもらったね。」
「ちょっとべたかなーって思ったけどー。けど、べたでもこれがカイに一番伝えたい、おれの気持ちだからー。」
ハウの目が、真っ直ぐに愛しいカイを見つめている。それから、ちょっぴり照れくさかったのだろう。「じつは渡したいものはもうひとつあってー」とハウは話題をそらすように続けた。
「ねー、インテレオン。」
ハウの目配せを受けて、インテレオンがゆっくりとカイの前に移動した。
「どうしたの、インテレオン?」
カイの質問に答える代わりに、インテレオンはぱっとかがんで膝を付いた。そして、1輪の青いバラをカイに差し出した。インテレオンの皮膚の色にも似た、深い青の美しいバラだった。
「わあ……きれいな青バラ。」
カイはインテレオンのプレゼントを受け取った。
「ありがとう、インテレオン!」
「インテレオンはねー、ゴリランダーの花かんざしとエースバーンの花冠が、ずっと気になってたみたい。でもインテレオンは花をもらうよりも、あげるほうがいいんだって。それでおれと一緒に、カイにあげる花を選んだんだ。良かったねー、インテレオン。カイに喜んでもらえて!」
インテレオンは満足そうにうなずいた。それから立ち上がって歩きだすと、今度はハウの前で膝を折り、1輪の青いバラを差し出した。ハウは目を丸くしてインテレオンを見つめた。
「えーっ、インテレオン、おれの分も用意してくれてたのー!?」
きっとインテレオンはハウに内緒で、青バラを2本お願いしたのだろう。サプライズに協力する花屋の店主の計らいがたやすく想像できて、カイはダズンローズの花束と1輪の青バラを抱え、くすりと微笑んだ。
それからカイとハウは、心からのお礼と共に、預かっていたモンスターボールとダイマックスバンドをカシダ氏に返した。ポケモンたちは今日の思い出のおかげで、カイとハウとの別れがますます惜しくなってしまったようだ。でも、これ以上はもうどれだけ先延ばしにしても、お互い辛くなるばかりなのは明らかだった。2人はめいめいに、3体と固く抱き合った。
今日は本当にありがとう。
とっても楽しくてどきどきする1日だったよ。
もらったプレゼント、大事にするね。
きっとまた一緒にバトルしようね!
きみたちのこと、絶対に忘れないよ!
言葉が通じなくたって、彼らの思いは少しも違わず、互いの心に届いていた。
バレンタインディナーにぴったりの、シュートシティのちょっといいレストラン。いろいろあったけれど、カイとハウは無事その予約時刻に間に合った。
2人が向かいあって座るテーブルの上には、花瓶が1つ置かれていた。それに生けられて華やかに空間を彩るのは、12本の真っ赤なバラと、2本の濃青のバラだ。カイが花束を抱えて入店するのを見て、店員が気を利かせて花瓶を用意してくれたのだった。
「とっても綺麗。」
カイがバラを眺めながらうっとり言うと、
「おれもそう思う。」
ハウも同意した。もっともその瞳には花ではなく、カイが映っているようだったけれど。
「今日はすごい1日だったねー。もー、大スペクタクルって感じー。」
「ポケモンたちとお散歩しながらのんびり過ごすバレンタインデーの予定からは、ずいぶん離れちゃったけどね。」
あははー言えてるー、とハウはからからと口を開ける。
「でもおれは、大冒険のバレンタインデートもいいなって思うよー。カイと一緒なら。」
カイとハウがにっこり笑み交わした時、ファーストドリンクが運ばれてきた。
穏やかなBGMと共にゆったり流れる時間と、想いのこもったかぐわしい贈り物、そして愛しい人の微笑み。
カイはグラスを掲げた。
「ハッピーバレンタイン、私のアローラ。」
ハウも応じてグラスを手に持つ。
「ハッピーバレンタイン、おれのアローラ。」
口付けのように優しく2つのグラスは重なって、澄んだ音が空気に溶けた。

