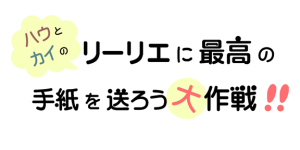15. ククイとバーネットの写真
前編 後編
カイとハウがククイの研究所を訪れたのは、西空で真っ赤に燃えていた炎の勢いもすっかり穏やかになった、黄昏時だった。
最初に訪れた時、あいにくククイが留守だった。戻ったら教えてくれるようバーネットに頼んでいたのだが、つい先ほど連絡が入った。「ククイが帰ってきたからいつでも遊びに来て」とのこと。さっそく今から会いに行ってもいいか尋ねると、快く了承してもらえたので、カイとハウは急いで海辺の研究所までやって来たというわけだった。
「いよいよ最後の一枚だねー。」
感慨深くハウが言う。その心にはきっと、再訪したアローラのいろんな景色と、みんながリーリエのために寄せてくれた数々の言葉が思い浮かんでいた。
「すごく濃厚な旅だったけどー、終わってみればあっという間だった気もするなー。」
「ほっとするのはもう少し先だよ、ハウ。最後の一枚も、最高の写真撮ろうね。」
カイに言われてハウは、そうだった、と表情を引き締める。
「よーし、おれは準備万端! カイはー?」
「もちろん大丈夫!」
二人は互いにうなずきあうと、研究所の扉をノックし、「アローラー!」と声をそろえた。
「やあ、カイにハウ! アローラ!」
扉を開けて迎えてくれたのは、鍛えあげた上半身に白衣をひっかけたいつものスタイルに、満面の笑みをたたえたククイだった。続いてイワンコの元気な鳴き声。さらに「アローラ!」と顔を出したのはバーネット。
「待ってたわよー! さあ上がって上がって。」
夫妻は二人を招き入れると、リビングのソファを勧めた。言われるままにカイとハウは荷物を降ろして腰かける。身じろぎが落ち着いた頃、バーネットがティーセットを運んできた。
「アーカラ島産のハーブティーよ。アローラに古くから生えている植物なんだけど、ロゼリアの花びらと煎じるといいってことが発見されて、今けっこう話題なんだって。」
そんな説明をしながらポットを傾けてティーカップに茶を注ぎ、二人の前に置いてくれた。薄黄緑色の液体からぽわんと草の香りが漂って、ちょっとシェードジャングルを思い出させた。いただきます、と言って茶を飲むと、思ったよりもさわやかな香りとあっさりした味わいが口の中に広がり、喉を潤した。
「バーネットから聞いているよ。リーリエにみんなの写真と寄せ書きを送るんだって? すごくいい考えだね!」
ククイが二人の向かいに座り、自分とバーネットの分の茶を注いだ。バーネットはありがとうと言って、ククイの隣にかける。
写真も寄せ書きもハウの発案であることをカイが教えると、ククイはさすがハウ、と付け加えた。ハウはえへへーとはにかんだ。
「最初にここへ来てくれたんだろう? すまなかったね。ちょうどその時、留守にしていて。」
「いえいえ、忙しいところすみません。」
「そう、大忙しだったんだよ! アローラリーグの広報に行ったら、珍しい技を使うポケモンがいるって情報が入ってね。もうあっちこっち高速移動さ!」
どこそこのエリートトレーナーが、アローラチャンピオンに挑戦するのを心待ちにしていたとか、イッシュ地方に生息するポケモンが今までに観測されたことのない技を使ったとか、事情を話すククイの顔は、大忙しと言いながらも楽しそうにきらきら輝いていた。
バーネットがそんなククイを優しく見つめながら、ティーカップに口をつけた。
「おっと、ぼくの話はこれくらいで羽休め。寄せ書きと写真だよね。」
やっと一息ついたククイがそう言ったのをきっかけに、カイの鞄がもぞもぞと動いた。カイが鞄を開けてやると、
「ボクの出番ロトー!」
ロトム図鑑が勢いよく飛び出した。
「やあ、ロトムも元気そうだね。」
とククイが挨拶する。
「元気いっぱいロト! さっそく一枚、はい、アローラ!」
カイが両手に持つのを待たずして、ロトムはカメラモードを起動させた。いきなり登場した赤いやつに遊んでもらえると思ったのか、イワンコがぴょんっとレンズに接近する。バーネットも反射的にククイの隣に身を乗りだして笑顔を見せた。
パシャッ!
「わー! いい写真が撮れたロト!」
見て見て! とロトムがカイの腕の中に飛びこんできた。映しだされていたのは、画面いっぱいにあふれるククイとバーネットとイワンコの笑顔の写真。きっとロトムは挨拶代わりの戯れにシャッターを切ったのだろうけれど、その割には、あるいはだからこそ、写った人たちはとても自然体で生き生きして見えた。
「これは、とってもいいねー。」
ハウがのぞきこんで目を輝かせた。カイにも異論はない。
「私の出番なくなっちゃったなあ、ロトム。」
わざとすねた口調でロトムを突っつくと、ロトムは少し慌てた様子でごめんなさいロト、と飛行高度を落とした。カイは冗談だよ、と笑って手のひらを広げ、ロトムをなでてやった。
「最高のロトムが私の図鑑に入ってくれて、すごく嬉しい。」
「ビビビッ! ほ、ほんト?」
三人のやりとりを聞いて、ククイとバーネットもわくわくした顔でロトム図鑑の周りに集まった。手のひら返しで誉められてまだびっくりしているロトム図鑑の画面を、カイは二人に差しだして見せた。
「わーお! ロトムって図鑑機能だけじゃなくて、撮影技術もすごいのね!」
「これはぜひリーリエにも見てもらわなくっちゃね。ぼくたちが元気でやってるってこと、一目で伝わるよ!」
夫妻もとても満足そうだった。立て続けに称賛を受けたロトムはすっかりご機嫌になり、文字通り天井まで舞い上がった。
 イワンコはせっかく赤いやつが遊んでくれるかと期待したのに、なんだかそういう雰囲気ではないことにがっかりしたみたいで、くうんと鼻をならした。ククイがイワンコの頭にぽんぽんと触れ、抱きあげた。
イワンコはせっかく赤いやつが遊んでくれるかと期待したのに、なんだかそういう雰囲気ではないことにがっかりしたみたいで、くうんと鼻をならした。ククイがイワンコの頭にぽんぽんと触れ、抱きあげた。
それからハウが寄せ書きの紙を出し、ククイとバーネットは思い思いにリーリエへのメッセージを綴った。
「これでおれたちの二周目の島巡りも無事終了だねー。」
ハウの言葉にククイは、なるほど二周目の島巡りか、とうなずく。
「それはいい発想だね。あ、そうだ島巡りといえば、きみたちに預けたい物があるんだよ。」
預けたいもの? と首を傾げるカイとハウを尻目に、ククイはイワンコを降ろすと足早に地下へ向かった。バーネットはにこにこしていたので、きっと何か知っているのだろう。
すぐに戻ってきたククイが手にしていたのは、片手にぎりぎり収まるぐらいの大きさの小箱。
「博士ー、これ何?」
尋ねるハウにぱちっとウィンクして、ククイは箱を開けた。
中に入っていたのは、新品の島巡りの証だった。
「これを手紙と一緒にリーリエに送ってほしいんだ。いつでもアローラに帰ってきてねって、ぼくらの思いを込めたプレゼントさ。バーネットと二人で考えたんだよ。」
カイとハウはしばらく目を丸くしてそれを見つめていた。
海の恵みを象徴するフィッシュテールを、四つの島を表す色に塗り分けた木製のアミュレット。アローラの島巡りトレーナーにとって、ポケモンと共に冒険することを決意した証であり、それを持たせてくれた人々の祈りと願いがこもったお守りだ。カイとハウのそれはもう、一緒にいろんなことを経験して世界に一つだけのぼろぼろになったけれど、箱の中の島巡りの証はまだ傷ひとつなく、持ち主を待っていた。ポケモントレーナーになってアローラに戻ってくると言ったリーリエの、約束が果たされる時を。
「すごい……リーリエきっと喜ぶよー! ありがとうククイ博士、バーネット博士ー!」
大切に箱のふたを閉め、嬉々として礼を述べるハウに、夫妻はにっこりとうなずいてみせた。
「で、二周目の島巡りはどうだったんだい? 一周目とは違う景色が見えたんじゃないかな。」
「うん! 島巡りに比べたら短い期間だったけど、たくさん美味しいもの食べたしー、カプの遺跡にもお参りしたしー、それから……」
誰と出会った、どんな話をした、ポケモンの様子はこうだった……。共に時間を重ねた二人旅の様子を、ハウとカイはククイたちに語り聞かせた。
だからその最後に「でも」とハウが逆接を続けた時、ククイとバーネットが眉を上げたのは当然だった。
「楽しいことばっかりじゃなかったんだー。スカル団の人たちと会って……。」
スカル団、と聞いてククイの表情は険しさを増す。ハウの横顔はしかし、思ったよりも前を向いていて、ゆっくりと丁寧に言葉をつないだ。耳にしたうわさ。グズマの写真。スカルマークを捨てたプルメリたち。反対に、いまだにそれを身に付けたままの残党たち……。
「おれ、拒絶していたんだ。スカル団の人たちのことを。最初の島巡りの時からずっと。だけどそんなんで向き合えるわけなかったよね。スカル団の人たちとポケモンバトルしたこともあるけど、結局おれはその度にあの人たちのポケモンと心を、傷付けただけだった。この旅でそのことに気がついて、おれ……おれは……。」
ハウは言葉を探す。ククイとバーネットは彼が答えを見つけるのを信じ、じっと口を閉じていた。カイも、たぶん理由は分かっていないイワンコも、ハウの表情を見守った。
「悲しい。悲しいし、情けない。」
難しい単語をたくさん並べて重ねるよりも。短く紡がれたその音は、涙のように透明だった。
ククイはそっとハウの肩に手を置いた。
「スカル団員たちのことは、ぼくもこのままじゃいけないと思っている。ハラさんもかなり気にかけているみたいだし……。」
ハウはちょっと目を開き、じーちゃんが、と繰り返した。ククイはうなずいた。
「きっとなんとかできるさ。だってハウにはポケモンたちも、島巡りで出会った大切な人も、側についてくれてるだろう?」
ハウはボールホルダーへ手をやり、モンスターボール越しに相棒たちに触れた。それからゆっくりと首を動かして、カイの方を見た。
カイは微笑み、力強くうなずいた。
真っ直ぐにこちらを見つめるハウの唇が、やわらかく上向きに弧を描いた。
「ありがとー、ククイ博士。」
ハウはククイに向き直り、言った。
「どういたしまして。もちろんぼくやバーネットのことも、ド忘れしちゃ嫌だぜ。いつでもきみたちの力になるよ。」
ダーリンの言う通りよ、とバーネットが裏付けした。イワンコも「わん!」と吠えて、自分もいるよと主張した。ハウは少しかがんで、イワンコの頭をなでてやった。イワンコは嬉しそうに目を細め、首の岩をハウの体にすりつけた。
「また遊びにきてくれよな。ハウも、カイも。」
「はい。ハーブティー、ごちそうさまでした。」
「すっごくいい香りで、美味しかったよー。」
「気に入ってもらえて良かったわ。また仕入れとくわね。」
そしてカイはアローラの人と景色とポケモンの写真がいっぱいつまったロトム図鑑を、ハウはいつかリーリエと共に旅をするだろう島巡りの証が入った箱と寄せ書きを、それぞれの鞄に大切にしまって、ククイの研究所を後にした。夫妻とイワンコは玄関先に立って、二人が見えなくなるまで手を(イワンコはしっぽを)振ってくれた。
 夜のとばりはすっかり降りていた。ククイたちと楽しく話しこんでいるうちにかなり時間が経っていたらしい。東の水平線の上には、海水浴を名残惜しむようにゆっくりと昇ってきた月が見えた。
夜のとばりはすっかり降りていた。ククイたちと楽しく話しこんでいるうちにかなり時間が経っていたらしい。東の水平線の上には、海水浴を名残惜しむようにゆっくりと昇ってきた月が見えた。
「小包を作らないとねー。」
一番道路のはずれを並んで歩きながら、ハウがほくほくした様子で言った。
「最初は手紙と写真だけの予定だったから、封書で送るつもりだったけどー。これがあるから。」
背負ったリュックを軽くゆすってみせる。リーリエ宛に預かった小箱が、中でかたっと音を立てた。
「包装紙と梱包材はたぶん家にあると思うからー、カイ明日おれん家に来て包むの手伝ってくれない?」
「いいよ。じゃあ写真印刷して持っていくね。あと引越しの時に使った荷造りひもも残ってると思うから、持っていく。」
「わー助かるー。あっ、最初に言ってた、リーリエへの手紙は用意できそう?」
危ない、忘れかけていた。でもリーリエに伝えたい話はたくさんあるから、筆が止まって困ることはないだろう。今夜手紙を仕上げれば大丈夫だ。カイは首を縦に振った。
「うん、なんとか書けると思う。」
「ありがとうー。さっすがカイ!」
ハウの歓声に、ぐううっと同意した者がいた。ハウの腹の虫だった。もうお腹もぺこぺこだ。照れ笑いと忍び笑いをくすくす重ねた後、二人は「じゃあまた明日」とリリィタウンへの分かれ道でさよならの挨拶を交わそうとした。
先にはっとして表情を固くしたのはハウだった。彼の異変を見たカイがその視線の先に目をやると、一番道路の向こう、リリィタウンへ続く道の途中に、二人の男がいた。
頭にはどくろを模した白いバンダナ。首から下げているのは鈍く光るスカルマークのペンダント。闇に溶ける黒ずくめに身を包んだ彼らは、間違いなくスカル団の残党だった。それも、写真撮影の旅で再三出会ってきた、グズマの写真を落としたあの二人組だった。そうだとすぐに知れたのは、彼らもまたこちらを指して「あいつらじゃないっスカ! グズマさんの写真、どーするっスカ!?」などと覚えのある語尾で相談する声が聞こえたからだ。
カイはぴりっと緊張してハウの様子をうかがった。ハウはどうすべきか答えを探して身動きできずにいた。その数秒の間に、スカル団の男たちは結論を出した。
「どーするもこーするもねえ。おれら今、最高に最低な気分なんだよ。気に食わねーからブッ壊す! ついでにグズマさんの写真も返してもらう!」
そしてモンスターボールを取り出した。低い月の光をきらりと反射した紅白の輪郭が、開閉スイッチの押下によって分かたれる前に、
「待って!」
ハウの口が開いた。男たちは予想外に飛んできた発言に思わず動きを止める。ハウはすうと一つ息を吸った。
「おれは、ポケモンを出さない。」
凛として落ち着いた口調の宣言だった。相対者たちは意図が分からず、次の行動を選べない。
「おれはきみたちとバトルするつもりはない。グズマさんの写真も返す。でもその前におれは、」
ハウは真っ直ぐにスカル団の男たちを見据えた。彼らは混乱し、たじろぎつつも、ハウの視線からは逃げなかった。逃げられなかったのかもしれない。いずれにせよ、それを確認してハウは言葉を続けた。
「きみたちと話がしたいんだ。」
片方の男が相方に何かささやいた。ささやかれた方は返事というよりもむしろ、自分も答えを知らない問いかけを突っぱねるような形で、短く乱暴な音を返した。
「反省したんだ。おれ、スカル団の人たちって島巡りを邪魔する悪いやつらだって、思いこんでた。島巡りを始めた時から……ううん、たぶんその前から、ずっと。周りの人たちの意見を考えなしに受け入れて。」
ハウの足が一歩彼らに向かって踏みだす。
「きみたちのこと何も知らなかった。知ろうとしなかった。ごめんなさい。だから、聞かせてほしいんだ。スカル団がきみたちにとってどんな存在なのか。きみたちがこれからどうしたいのか。どんな思いでグズマさんの写真を撮ったのか。」
スカル団員たちは今、この暗闇の中で遠目に見ても分かるくらいに、困惑していた。全身にみなぎっていた敵意はその戸惑いに圧されて小さくしぼみ、腕は下に垂れて、握りしめたモンスターボールは地面を向いた。けれども彼らの口は、ハウの問いに答えるために開くまでには至らなかった。
しばらくして沈黙を理解したハウは、おもむろにリュックを下ろし、一枚の紙を取り出した。グズマの写真だった。
「これ……。」
夜の中でも見えるように、ハウは右腕をいっぱいに伸ばし、それを彼らの方へ向かって差し出した。月が写真を光で照らし、ハウの気持ちに助け船を出した。
「返すよ。きみたちの、グズマさんの写真。」
男の一人がはっとして身じろぐのが分かった。しかし彼らが写真を受け取るためには、ハウに近づかなければならなかった。一瞬グズマの写真の方に傾いた体重をそのまま足に乗せて踏みだして、歩み寄らねばならなかった。それはきっと勇気のいることで。壊すとかポケモンバトルで力ずくでとか、今までずっと選んできたのと違う選択をするということで。考えるのをやめて、拒絶するなら簡単だった。
「ふ……ふっざけんなよ。今さらいい子ちゃんぶってんじゃねえよ。」
そして彼らは、簡単なほうを選んだ。
「お前は何にも分かってねえ。なんっにも! いいか、お前がそんな偉そうなこと言ってられんのは、運が良かっただけだからな。たまたま、恵まれた環境ってやつにお前がいただけだからな。お前なんか……お前なんか、しまキングの孫って肩書がなきゃ、何もできないくせに!」
頭に血が上るスピードで言えば、たぶんハウよりもカイのほうが速かった。しかしカイはそれとほとんど同じ速度で、この怒りを口にするべきではないことも直感した。今カイが怒りに任せて行動すれば、モンスターボールを手に取らなかったハウの選択を粉々に壊してしまう。だからカイは何も言えなかった。ハウも、黙ったままだった。
わめくだけわめいたスカル団員は、きびすを返して逃げだした。ハウが差し出した写真に一瞬反応したほうの男は、少しその場に留まっていたが、「何やってんだ行くぞ!」と相方に腕を引っ張られると、すぐに行動を共にした。
暗闇に消えたスカル団員たちの後ろ姿を、カイも、ハウも、ただ見送ることしかできなかった。
「ハウ……。」
伸ばした腕を下ろし、真っ黒な一点を見つめ立ち尽くすハウの背中に、カイはそっと声をかけた。振り向いたハウは月明かりに濡れ、今にも泣きだしそうな顔で微笑んだ。
「やっぱり、上手く、いかないねー。」
それは痛々しいと表現するにはあまりにも覚悟を決めた、儚げと表現するにはあまりにも意思を秘めた、悲しい笑みだった。
そんなハウの目を見てカイは、考えるよりも早くハウの左手を両手に包んでいた。爪が食いこむほど固く結ばれた彼の手は、石のように冷たく、小刻みに震えていた。
「でも、ハウは拒絶しなかった。」
カイの瞳に映った自身の姿を、ハウは見たかもしれない。拒絶することに逃げず、一歩踏みだした少年の姿を。
かすれた声で、ハウは答えた。
「ありがとう、カイ。」
凍えた石ころがふわりと形を崩し、徐々に体温を取り戻す。側についてくれている人の存在を感じて、体の震えは治まりかけていた。
月は昨日とは違う形で、夜を優しく照らしていた。