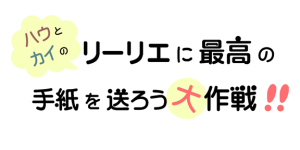14. グラジオの写真
1 2 3
「じゃあグラジオ、シルヴァディ、撮るよー。二人ともカイのほう向いて笑ってー。」
「そんなこと言われても、シルヴァディは人間みたいな顔で笑うわけじゃない。」
「分かってるよー。どっちかって言うと、笑顔足りないのはグラジオだよねー。シルヴァディはすごく嬉しそう。」
「わっ、こらシルヴァディ、ちょっと待て……。」
グラジオの制止を聞かず、ごきげんなシルヴァディがその愛情を文字どおり頭から伝えた瞬間、「シャッターチャンスロトー!」とロトムの声が響く。パシャリ。グラジオの髪の毛を満足げに食むシルヴァディと、相棒の舌にべっとり挨拶されて困惑とも微笑みともつかない顔になったグラジオが、ばっちりロトム図鑑の画面に収まった。
グラジオが戻ったとビッケから連絡が入ったのは、その日の朝一番のことだった。カイとハウはすぐさま身支度を整え、エーテルパラダイスに向かった。
存外早かったなと驚くグラジオは、すでにビッケから大体の経緯を聞いていて、リーリエに手紙を送ろうとしてくれていることに感謝の意を述べた。さらにエーテル財団の代表代理として、財団の不始末の収拾に手を貸してくれたことに改めて頭を下げた。なんだかちょっと見ない間にグラジオは、ずいぶん背が伸びたようだ。
「あれはおれたちも、島巡りの一環みたいなもんだったからー。それより早く写真撮ろー! グラジオの写真、リーリエ絶対喜ぶよー。」
ハウが口早にそう言って写真撮影の開始を促したのは、たぶん彼もそんなグラジオを見上げるのが、ちょっぴりくすぐったかったからだろう。
グラジオの写真撮影の背景として選んだのは、エーテルパラダイス二階の保護区だった。ガラス越しのやわらかな陽光が降り注ぐ中、保護されているポケモンたちの穏やかな鳴き声をBGMに、カイとハウとグラジオは撮影結果を確認していた。ロトム図鑑の小さな画面に顔を寄せ集め、撮影した写真のどれをリーリエに送るか、あれやこれやと相談する。
「おれ絶対これ。ぜーったいこれがいいと思う。」
ハウの一押しは、グラジオがシルヴァディに頭からかじられている例の写真だった。カイもこれはかなりよく撮れたと思う。保護区内のポケモン、ツツケラとケララッパが飛んでいくのが偶然写ったのもポイントが高い。
「それに何よりグラジオの表情がいいよねー。じゃれつかれて嬉しいみたいな、食べられそうでどうしようみたいな。」
「…………。」
当のグラジオは、写真の表情に負けず劣らず微妙な顔をしている。こんな姿を妹に見られるのは恥ずかしいみたいな、シルヴァディが心を許してくれていることに感じ入っているみたいな。
「オマエたちの、好きにすればいい。」
でも結局そう言ってくれたので、カイとハウは遠慮なくその写真を選んだ。まだ甘え足りないのかグラジオに体をすり寄せているシルヴァディも、とても幸せそうに見えた。
「忙しいところありがとう、グラジオ。」
その後、寄せ書きを書き始めたグラジオを見守りながらカイは言った。グラジオは最初、それを書くつもりはなかったようだ。家族として連絡は取りあっているのだから、わざわざ寄せ書きの形でリーリエにメッセージを送るのも気恥ずかしかったのだろう。けれど他のみんなが妹に対してどんな言葉をかけてくれているのかは気になったようで、「見るだけでも構わないか?」と尋ねたところ「グラジオも書いてくれるならいいよー」とハウに交換条件を突きつけられたので、結局ペンを手に持ったというわけだった。
礼には及ばないさ、とグラジオは首を振った。
「今日は休日なんだ。だから問題ない。」
「そうだったんだー。なんか逆に申し訳ないなー。エーテル財団代表の貴重な休日にお邪魔しちゃって。」
「代表代理、な。ビッケとか他の職員たちもだいぶ助けてくれるから、ちゃんとオンオフの区別はできてる。」
「それはなにより。」
「ああ。だから、この後も特に予定は入れていないから……その。」
もごもごとグラジオは急に口ごもってしまった。今日は休日、このあとも予定は入れていないから、とくれば続く言葉に迷うことはなさそうなものだが、何を遠慮しているのだろう。スカル団にいた時の所業や、家族のことを負い目に思っているのか。あるいは以前「オレたちは仲良しではない」なんて自分で言ったことに整合性がつかなくなって困っているのか。
ハウがカイを見て、肩をすくめた。
「……一緒にお昼ごはんでも?」
カイが提案すると、グラジオは気まずそうにうなずいた。
「もー、素直じゃないなーグラジオ。」
くすくすとハウが笑った。
「いいえ、ぼっちゃまとお呼びしていた頃に比べれば、それはもうずいぶん大人になられたんですよ。」
三人の元に現れたのは、ビッケだった。ちょっといたずらっぽい表情をやわらかく浮かべて、こちらに歩み寄る。
「小さな頃、リーリエお嬢様と喧嘩をされたことがありましてね。確か、お母様のピクシーにおやつをあげる時だったと思うのですが、お嬢様が先にあげたいと仰っていましたのに、ぼっちゃまが先にあげてしまいまして。泣いてしまったお嬢様へのお詫びにって、ぼっちゃま、明日のぶんのポケモンのおやつを綺麗な紙に包んだまでは良かったんですけど、それをなかなかお嬢様に渡せなくって……」
「そ、その話は、今はいいだろう! どうしたんだ、ビッケ。」
「ああ、そうでした。連絡船の準備が整いましたので、ご報告に参りました。ハウオリ行きで間違いないですよね。」
「わー、ビッケさん用意いいねー!」
ハウが目を丸くする。ちょうど今、一緒にご飯に行こうとグラジオを誘ったところだった旨をカイが補足すると、ビッケはあら、と首を傾げた。
「今日はカイさんたちと一緒にお食事をする予定だって、グラジオ様から聞いていたのですが。ハウオリショッピングモールに行かれるんですよね?」
それは初耳だ。カイとハウは同時にグラジオへ視線を集めた。
グラジオは二人から顔を背けると、書き終えた寄せ書きをハウに押しつけるようにして渡し、「行くぞ」とだけ短く伝えた。そのままそそくさと乗船場へ降りるエレベーターへ行ってしまう。シルヴァディが後に続いた。
カイとハウは、ビッケと顔を見合わせた。照れて口ごもったグラジオの言葉の続きをカイが拾ってしまったけれど、やっぱり本当はグラジオのほうから二人を昼食とショッピングモールに誘うつもりだったのだろう。
「まだ、ぼっちゃまって呼んでもいけるかもよー?」
ハウがにやっと笑うと、ビッケは口元に手を当てて「考えておきます」と答えた。
それからビッケは乗船場まで同行し、三人を見送ってくれた。
 「なんでショッピングモールに行きたいと思ったのー?」
「なんでショッピングモールに行きたいと思ったのー?」
カイ、ハウ、グラジオの三人でモール内を並んで歩きながら、ハウはグラジオに尋ねた。船の中でも同じ質問をしたのだが、なぜだかグラジオは「降りたら教えてやる」の一点張りで、答えてくれなかったのだ。
無事に船を降りたので約束の答えを求めたわけだが、グラジオはやっぱり口をつぐんだまま。ははあ、これはまた何か恥ずかしがっているな? とカイとハウが勘繰った時、
「クッキー屋があるのを、知っているか。」
グラジオはそう言った。
そういえばハウオリショッピングモールに、なんとかのクッキーショップがオープンしたという話を聞いたような気もする。モモンとかブリーとか、きのみをふんだんに使った自然派クッキーで、ポケモンも安心して食べられるのが売りらしい。ただ、その手の広告はよく目にするから、それがグラジオの思っている店と一致するのかは自信がなかった。
ハウも似たような感じで記憶を探っていたが、一応「そういえばあったかもー」と答えた。
「その店のクッキーが欲しいんだ。財団の職員たちが話しているのを聞いて……形が可愛くて美味しいとかで、食べてみたいって……その、母がああなって以来、ばたばただったろ。ずいぶん迷惑や苦労もかけたと思うから……礼にもならないかもしれないが……」
プレゼントか。だから財団職員が一緒にいる船の中では話したくなかったのだ。事情を理解したカイは、思わず頬をゆるめた。ハウも同じ顔をしていた。そしてハウは、本当に素直じゃないねーグラジオは、とでもこぼしかけたのを腹に収める間を取った後、
「あそこにモールの案内板があるよー! クッキー屋さんどこにあるか見よー!」
たたたっと道を駆け、カイとグラジオに向かって手を振った。
グラジオはそんなハウの背中をゆっくり歩いて追いかけながら、
「本当に落ち着きがないな、ハウは。」
とこぼした。
案内板の上でクッキー屋の場所はすぐに見つかった。が、今カイたちがいる場所からは少し離れていた。それで三人はモールの中をぷらぷらと歩きながら、目的の店を目指すことにした。
ポケモン用衣類のブランド店、ヤミラミをロゴにあしらった宝石ショップ、いかにも観光客向けの花飾りや土産用菓子の箱をずらっと並べたチェーンストア……。店舗の内装も外装も、通路や壁に植えられた様々な植物も、思い思いにショッピングモール内を彩って、まるでアローラ中の色が一堂に会しているようだった。
グラジオは右に左に顔を動かして、そんなにぎやかな虹色と、その中を行き交う人やポケモンの様子を眺めていた。
「グラジオはショッピングモール、あんまり来ないの?」
カイが声をかけると、グラジオは「うん」と答えた直後、視線をぱっとこちらに寄越して「ああ」と言い直した。
「スカル団にいた頃は、ヌル……シルヴァディを鍛えることしか考えていなかったから……。」
「そうなんだー。じゃあ気になるお店があったら入るといいよ。ゆっくり行こー。」
と言いながら自分のほうがショーウィンドウをのぞきに行っているハウに、グラジオは何かまた尖った言葉の一つでも投げつけるかと思ったら、
「……そうだな。ありがとう、ハウ。」
素直にそう言ったので、カイは思わず目を丸くしてグラジオの横顔を見た。
ただ、
「そんな小さな声じゃ、ハウには聞こえないよ?」
と指摘したカイには、うるさいなっ、とツンツンに尖った声が返ってきた。照れ隠しだった。
結局カイとハウとグラジオは、帽子屋でシルヴァディ色のキャップをグラジオに被せてみたり、アローラ・フラを踊るドレディアを連れた客引きに呼ばれたり、ステージ広場のライドポケモンショーに足を止めたりで、五分で歩ける距離を一時間くらいかけて目的のクッキー屋に到着した。
「そういえば今日の目的って、クッキーだったね。すっかり忘れてたよー。」
可愛らしいポップカラーのポケモンときのみのイラストで飾られたクッキーの店舗に入った時、ハウは冗談抜きにそう言った。
いろんなきのみの形をした店内のクッキーを見て、グラジオは「これだ、職員たちが言っていたやつ」とほっとした様子だった。早速、詰め合わせの箱を物色し始める。
その間カイとハウは暇だったので、味によって異なるきのみを模しているクッキーを眺めたり、パッケージに描かれているポケモンについて話をしたりした。花の代わりにたくさんのきのみをぶら下げて運んでいるキュワワーのイラストが、ハウは特に気に入ったそうだ。試食もさせてもらった。ポケモンへの試食も促されたので、ルガルガンやライチュウをボールから出してわいわいしているところに、グラジオが買い物を終えてやって来た。
「わー、かなり買ったねー!」
グラジオが提げている紙袋の大きさを見てハウがちょっと驚いた声を出す。グラジオは満足そうにうなずいた。
「これだけあれば足りると思う……みんな喜んでくれるといいんだが。オマエたちも、付き合わせてしまって悪かったな。」
「いえいえ。ロンウルもクッキー試食させてもらって嬉しそうだし。」
口回りについた食べこぼしをぺろんとなめとり、わふ! と吠えたカイのルガルガンに、グラジオは優しい眼差しを向けた。
「オレたちも腹が減ったな。」
「ゆっくり来たからもうとっくに十二時回ってるもんねー。お昼ごはん、どこで食べようか? バトルバイキングもそろそろ席空いてるかもしれないしー。」
「バトルバイキングも興味があるが……。」
グラジオは少しためらいがちに、それでもカイたちとショッピングモールに行きたいことを言い渋った時よりはあっさりと、口にした。
「ハンバーガーが、食べたい。」
 白い雲が浮かぶ真っ青な空。それよりももっと濃い青色の海に、波頭が白く光っている。空と海は同じポケモンから生まれた、なんておとぎ話を聞かされたら、今なら簡単に信じてしまえそうだ。
白い雲が浮かぶ真っ青な空。それよりももっと濃い青色の海に、波頭が白く光っている。空と海は同じポケモンから生まれた、なんておとぎ話を聞かされたら、今なら簡単に信じてしまえそうだ。
「潮風を浴びながら食べるランチは、格別だねー。」
そう言ってハウは、勢いよく手元のハンバーガーにかぶりついた。満足そうにもぐもぐしている口回りは、ソースでべとべとだ。カイがそう伝えると、ハウはぺろんと舌なめずりをしてそれを片付けた。ロンウルとおんなじ、とこっそり思うカイの前で、ハウはえへへと笑っていた。
カイとハウとグラジオは、クッキー屋での買い物を終えた後、ロッカーに荷物を預け、フードコートでハンバーガーをテイクアウトした。ビーチサイドエリアまで移動してベンチに腰かけ、海を眺めながらの青空ランチというわけだ。
潮風を好む厚葉の街路樹が、熱い日差しをやわらかな緑の影に変えて、三人の上に落としていた。
カイのジュナイパーとハウのアシレーヌとグラジオのシルヴァディが、向こうの砂浜の上で追いかけっこをしていた。ロトム図鑑も、海水に濡れないよう十分距離を取って、三体の上を飛んでいる。アシレーヌが海に逃げると、ジュナイパーはロトムに合流して上空をくるくる飛び、シルヴァディは足の先っぽだけを波に浸してがうがう吠える。一人で泳いでいるのもつまらなくなったアシレーヌが上陸するとまた三体そろって走り回り、砂まみれになったところでアシレーヌが海に入る。ジュナイパーとロトムが旋回する。シルヴァディはがうがう呼ぶ。そんなことを楽しそうに繰り返していた。今日はビーチで遊ぶのには、最高の天気だ。
「でも、グラジオならもう少し落ち着いたレストランとかが好みかと思ったよー。」
ハンバーガーを飲みこんでハウがそう言うと、「オレだってハンバーガーくらい食べるさ」とグラジオはすまし顔だった。その手に持っているハンバーガーからレタスが飛び出していなければ、完璧な絵面だったとカイは思う。
「エーテル財団のお仕事はどう?」
カイが尋ねると、グラジオは「ん」と短く返事した。落ちそうなレタスに気がついたようだ。
「大変なことも多いが、なんとかやってる。……オレはひとりじゃないからな。」
無事にレタスを確保して落ち着くと、そう答えた。
カイもハウも、最初に出会った頃からはずいぶん変化したグラジオのものの言い方に、自然と目を細めた。
「オマエたちはどうだ。島巡りを終えて、今は一息ついている、といったところか?」
「まあねー。リーリエに送る写真を撮って回って、二周目の島巡りって感じー。」
「ほう、いいじゃないか。スカル団も解散したと聞いたし、一周目よりも回りやすいぐらいじゃないのか。」
グラジオは何の気なしに言ったのだろう。しかしハウはその言葉を聞いて、動きを止めた。写真と寄せ書きを集めるこの島巡りに、スカル団の影が全くないとはとても言えなかった。むしろスカル団が解散したことで、それはよりいっそう深い混沌の色になったようにも見える。
カイとハウの表情の変化を、グラジオはすぐに察した。
「……何かあったのか?」
「あった、ってほどじゃないんだけどー……。」
ハンバーガーの包み紙をやたら丁寧に剥きながら、ハウはそう前置きして話し始めた。
写真を撮るため会った人たちから聞いたスカル団のうわさ。エーテルパラダイスでの事件がスカル団の暴動だったとして報道されていたこと。プルメリや元スカル団員たちの話。そして、今もスカルマークを身に付けたままどこかを放浪している、グズマを慕う二人組の男のこと……。
ハウが詰まったところは、カイがつなげた。そうして、島々を一周や二周した程度では変わりそうもない、アローラに色濃く落ちた影の色を、グラジオは二人と共に見つめてくれた。
話が終わった頃、喉を潤そうとハウが手に持ったサイコソーダのカップは、すっかり露に濡れていた。
「なるほどな……。」
グラジオは短く息を吐いた。それから、言葉を組み立てる時間を少し取った後、言った。
「拒絶するのは簡単だ。」
ストローから口を離したハウがグラジオを見る。
「オレはかつて、何もかもを拒絶していた。母のやろうとしていたことも、タイプ:ヌルが置かれていた環境も。そこに関わる人間が、どんな気持ちでどういう意図でその行動を取っているのかなんて、考えようともしなかった。ヌルのためだって自分に言い聞かせて、目も耳もふさいで。」
グラジオはシルヴァディに視線を向けた。
砂浜のポケモンたちは、今は追いかけっこを中断していた。アシレーヌがみんなにアリアを披露している。ロトムは青空リサイタルの写真を何枚も撮影し、それがますますアシレーヌの気分を良くさせたようだ。歌と一緒に虹色の泡を出し、宙に舞わせた。ジュナイパーとシルヴァディは泡に興味津々で、鼻先で触れては割っていた。それがぱちんとはじけるのが面白いらしい。歌うアシレーヌと、競うように頭を小刻みに動かしているジュナイパーとシルヴァディと、ぱちぱちはじける泡、そしてその様子をどんどん画面に収めていくロトム。
グラジオはちょっと口角を上げて彼らの戯れを見つめた後、いや、と独り言のように続けた。
「一番拒絶していたのは、たぶん、そうやって逃げている弱い自分自身だったのかもしれないな……。」
前髪をかきあげるようにして、左手を額に当てる。すっかりエーテル財団代表代理が板についたと思っていたけれど、それはよく見知ったグラジオの仕草で、カイはなんだか安心した。ちなみにいつもなら半身を覆うように右手を腰に回すのだが、今はハンバーガーでふさがっているので割愛されている。
ハウは、拒絶……と小さくつぶやいた。ゆっくりと手元に目をやり、しかし見つめているのはどこか遠くの時間と場所だった。それからしばらくするとふっと表情をゆるめて、あのさーグラジオ、と名前を呼んだ。
「まあまあ、かっこいいよ。」
「…………。」
グラジオがじとっとハウをにらんだのは、その言葉にちょっとからかうような響きが含まれていたからだろう。けれどもカイには見えていた。言葉の響きだけでは隠しきれない、どこか吹っ切れたような光の色が、ハウの目に宿っているのが。
ハウは残りのハンバーガーを一気に口へ押しこむと、ベンチから立ち上がり「ねー波打ち際まで行こうよー!」と二人を誘った。
「待て、オレはまだ食べ終わってない……」
「おれ先に行っちゃうからねー!」
ハンバーガーの包みをごみ箱に放り投げてナイスシュートを決めたハウは、もう砂浜に足跡を付けていた。遊んでいたポケモンたちの輪に加わって、楽しそうに「うーみー!」と叫んでいる。
「まったく……島巡りをしていた頃から全然変わらないな。むしろもっと子供っぽくなっているんじゃないのか。」
グラジオはあきれてため息をついたが、カイはそうは思わなかった。二人を置いて先に行ってしまったハウは、島巡りをしていた頃に比べると、ずいぶん遠い場所にいるように感じた。広がる景色に目がくらんでも、砂に足を取られても、ハウはきっと先に進むことをやめないだろう。なぜなら出会った人やポケモンの存在が、それらと共に時間を過ごした経験が、自分を支え導く標になることをハウは知っているから。
グラジオの言葉もきっと、今のハウに必要な標の一つだったのだろう。
「……ありがとう、グラジオ。」
「ん? 何がだ。」
「なんでもない! ほら、私たちも行こう。今日はビーチで遊ぶのには、最高の天気だよ!」
砂浜に躍りでたカイに、ハウやポケモンたちが駆け寄る。
「グラジオー!」
みんなで呼ぶと、グラジオはゆっくりベンチから立ち上がった。しかしそのまま移動しないので、やっぱりあまり気乗りしないのかと思ったが、よく見ると彼はズボンの裾をまくっているところだった。なーんだ、やる気十分だ。カイとハウはにーっと歯を見せ合うと、手を振ってようやくやって来たグラジオを迎えた。
そうして三人の若者とポケモンたちは、波間にきらきらとはじける光に、しばしの時間、身を浸した。