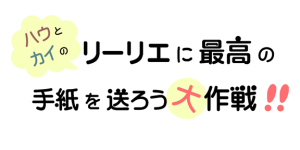13. プルメリと元スカル団員の写真
前編 後編
あー! とハウが大声を上げた。
「カプ・ブルルへの礼拝、忘れてたー!」
コケコ、テテフ、レヒレへの参拝を済ませ、ブルルにだけ挨拶しないというのはかなり具合が悪いだろう。なにせ相手は町一つ滅ぼすほどの力と気性の持ち主である。
そういうわけでカイとハウが乗りこんだエーテルパラダイス発の連絡船が、行き先をメレメレ島からウラウラ島へ変更したのが数時間前のこと。
無事に礼拝を終えた二人がハイナ砂漠を抜けて十三番道路に戻る頃には、日はとっくに天頂を通過し終えていた。
今日はモーテルにでも泊まろうかと話をする中で、そういえば、とハウがふと話題を変えた。
「ここってスカル団の人たちが集まってたよねー。」
道路の端に停まっているトレーラーハウスを見て、ハウはそのことを思い出したようだった。確かに島巡りをしていた時、ここでスカル団員たちがたむろしていたのを、カイも見た気がする。
「写真を落としたあの人たちも、いるかなー。」
遠目にトレーラーをのぞきながらハウは言った。彼岸の遺跡前で拾ったグズマの写真のことを気にしているらしい。スカル団員たちにいきなりポケモンバトルを挑まれ、あっという間に逃げられてしまった後、写真をあの場に捨て置くことなどできなかった。それでハウはグズマの写真を、とりあえず自分のリュックの中に収納していた。
「行ってみる?」
カイが尋ねると、ハウは気がかりな表情にぱっと花を咲かせ、うん! と答えた。
「えっ、えっ? スカル団に、会いに行くロ?」
二人を引きとめたのは、カイの鞄の中から不安そうに顔を出したロトムだ。カイは一瞬だけ答えを探したが、
「大丈夫だよ、ロトム。」
すぐにそう答えた。上手く根拠は言えないが、なぜだかそう感じた。
「写真、返すだけだからさー。」
ハウもカイの言葉に続く。二人に説得され、ロトムはちょっぴり不安な気持ちを残しながらも、ウン、とうなずいて大人しく鞄の中に引っこんだ。
かつてスカル団員たちがうろついていたトレーラーハウスの入口付近には、今は誰もいなかった。ハウは扉の前に立ち、ちょっとカイの方を見る。カイがうなずくと、ハウはドアをノックした。
「開いてるよ。入りな。」
中からくぐもった女性の声が聞こえた。さばさばとした喋り口だが、敵意はない。むしろ歓迎の温度さえある。
ハウとカイが中に入ると、はたしてそこにいたのは、スカル団幹部のプルメリだった。いや、彼女も今はグズマと同じように、どくろを模した髪留めもペンダントもタトゥーシールも外していたから、「元」スカル団幹部と呼ぶほうが正しいか。けれどもそんな肩書などなくたって、咲き誇る花のようなピンクと黄色に染めた髪と、彼女の隣に侍る相方のエンニュートが、プルメリの存在を変わらずプルメリたらしめていた。
「アローラ。」
カイとハウが控えめに両手で弧を描くと、プルメリはかなり驚いた顔を見せた。
「なんだ、あんたたちかい。」
先ほどよりは冷たい言葉だったが、それでもプルメリはごく小さなつぶやきで「アローラ」と続けた。それで、こちらをじろっとにらんでいたエンニュートも警戒を解いた。
「こんな所に何の用だい。」
「えっとー、この写真を落としたスカル団の人を探してるんだけど。」
「写真?」
いぶかしげに首を傾げ、プルメリはハウから写真を受け取った。そこに写っている人物を見て、少し目を開く。
「これ、グズマじゃないか。」
「うん。二人組の男の人たちが落としていったんだ。ちょっとたれ目の、スリープを使う人とー、えーと、」
「語尾にスカスカ付ける、ズバット使いの人と。」
「ああ、あいつらか。」
かなり少ない情報だったが、プルメリには伝わったらしい。まじまじと写真を見つめながら、なるほどね……こういう根拠があったのか、と独り言をつぶやいた。
「確かに二日ぐらい前だったか、あいつらはここに来たよ。」
「あのー、その人たちに写真、返しておいてもらえる? 大事なものだったみたいで。」
プルメリはしばらくグズマの写真を眺めていた。裏面を向け、もう一度表面を眺め、ふうと小さなため息をつく。それから、ハウに写真を返した。
「悪いけど、あたいはこれを預かれない。」
「えっ。どうしてー?」
プルメリは、すぐには質問に答えなかった。代わりに「座んなよ」と二人にソファを勧める。カイとハウがそれに従うと、向かいのソファに自分も腰かけ、語り始めた。
「グズマがスカル団の解散を宣言した後、」
エンニュートがゆらりとプルメリの背後へ移動した。
「団員たちの反応は様々だった。素直にグズマの意思に従うやつ、呆然と立ち尽くすやつ、怒ってグズマにかみつくやつ……。中でもこの写真を大事に持っていた二人組は、グズマのことは慕ってるけど解散は信じられないタイプのやつだった。
あいつら、あたいの所に来て言ったんだよ。スカル団を立て直そうって。姉御ならできるって。でもあたいは断った。そんでけんか別れさ。」
プルメリは肩をすくめ、寂しそうに苦笑した。
「だからあたいがあいつらにまた会える保証はない。『もう姉御なんて頼らないッスカら!』って言われちゃったからね。」
そういう事情であれば、確かにプルメリに写真を預けても仕方がない。と言って、自分たちが写真の持ち主でないのも変わらない。カイとハウが困って写真を見つめていたところ、プルメリは「たぶんそれ、証明写真用に撮ったんだろうねえ」と補足した。
「証明写真?」
「スカル団を解散した後あんたはどうすんだいって聞いたんだよ、グズマに。そしたらまあ、あんまり歯切れのいい返事じゃなかったけど、どこぞのバトル施設に行って鍛えるとかなんとか言ってたからね。おおかた、そのパスを作るために必要な写真を、あの二人組に撮らせたんだろ。」
「ずいぶんカジュアルなポーズの証明写真だねー。」
「普通に撮ったってスカしてないってもんさ。通るかどうかは知らないけど。で、あの子らはグズマにだいぶ懐いてたから、自分たち用にも印刷したんだと思うよ。」
「それならなおさら返さなきゃー。」
眉を下げたハウに、プルメリは、いや、と首を振った。
「だからこそ、この写真はあいつらの手元にないほうがいいんだ。」
「どういう意味?」
「いつまでもグズマの背中見てたって、何にもならないってことさ。スカル団は、もうブッ壊れちまったんだから。」
カイもハウも何も言えなかった。写真の中で動かぬ微笑みを浮かべるグズマをただ見つめるばかりの二人に、「それで?」と今度はプルメリのほうから質問した。
「あんたたちまさか、そのためだけにわざわざこんな所ほっつき歩いてたのかい。」
「だけ、ってことはないんだけどー。」
それでカイとハウは、カントーで暮らすリーリエに手紙を送ろうと思っていること、それに添えるアローラの人たちの写真をあちこち撮って回り、みんなの寄せ書きを集めている旅の途中であることを説明した。
なるほどね、とプルメリは唇の形をうっすらと上向きにする。
「リーリエがカントーに……。やっぱりあの子は強い子だねえ。」
一度はリーリエを連れだしてその身を隣に置いたからこそ、プルメリはリーリエが持つ芯の部分に感じるところがあるようだった。可愛がっているしたっぱたちの話をするのにも似た表情を浮かべるプルメリに、ハウは「あっ、じゃあさー」と口を開いた。
「せっかくだからプルメリさんの写真も撮らせてほしいなー。」
「あ、あたいの写真?」
予想外の申し出にプルメリが驚く。カイの鞄からは、ロトム図鑑がひょっこり顔を見せていた。写真と聞いて、自分の出番だと思ったのだろう。その使命感が先立つほどに、スカル団に対する不安はもう薄れたようだった。プルメリとのやり取りを聞いていたのかもしれない。ロトムが安心してくれて良かったと、カイはほっとした。
「うん! できれば寄せ書きもー。」
「いやさすがに寄せ書きは遠慮しとくよ。字だって汚いし……。」
「じゃあ写真だけでもお願いします。ロトムもやる気満々だし。」
カイが重ねて依頼すると、プルメリはカイの鞄から飛び出ている真っ赤なロトム図鑑をちらりと見た後、まあ写真くらいなら別にいいけど……あたいなんかでいいのかい……などともごもごつぶやいた。もちろんです、プルメリさんじゃなきゃだめなんだよー、写真はボクにお任せロト! と口々に伝えるカイとハウとロトム。それでプルメリも、なんとか腰を上げた。
部屋の中よりも外で撮ってほしいというプルメリの希望で、一行はトレーラーハウスを出た。
 「この辺でいいかい。」
「この辺でいいかい。」
エンニュートと一緒にオアシスの側に立ち、プルメリはポーズを取った。ポーズと言っても凝ったものではなく、背筋を伸ばして片手を腰に当てる程度のものだ。けれどもシンプルな立ち姿はかえって体の輪郭を際立たせる。トレーナーとポケモンは互いに似てくるとはしばしば言われることだが、プルメリとエンニュートにもよく当てはまっていた。二人ともきれいな体のラインだなあ、と思いながらカイがロトム図鑑のシャッターボタンを押そうとした時、
「でも、本当にあたいなんかの写真で大丈夫かい?」
不安そうな声と共にプルメリの美しい曲線が崩れた。ビ、とシャッターチャンスを失ったロトムが小さく声を上げた。
「あたい、あの時リーリエを無理やり連れ出したようなもんだからさ。その……嫌な記憶を思い出しちまわないかい? やっぱりやめといたほうが良くないか?」
普段の姉御肌で強気な様子からはちょっと想像がつかない、自信なさげな表情をプルメリは浮かべていた。こんな年相応にいじらしいプルメリの姿を、カイは初めて見た。それはたぶんハウも同じで、
「大丈夫だよー。リーリエはそれも全部含めて、アローラのみんなに会えてよかったって思ってくれてると、おれは思う。リーリエ、意外と強い人だからさー。」
そう言ってプルメリを励ました。カイもハウに同意する。エンニュートが鼻面をぐいとプルメリの頬に押しつけた。それでプルメリも、エンニュートの頭を撫でてやりながら表情を和らげた。
「そうかい……。まあ、あんたらがそう言うなら。」
揺れた背筋を再びしゃんと伸ばして、エンニュートと共に凛々しく立つプルメリ。その姿をもう一度ロトム図鑑の画面に捉えて、カイがシャッターを切ろうとした、その時だった。
「姉さん!」「プルメリの姉御!」
シャッターチャンスは再びおあずけを食らった。ビー、とロトムが今度は明らかに不満げな音を出した。
声の聞こえた方を見ると、二人の男女が真っ直ぐこちらに向かってやって来ていた。髪を青やピンクに染め、黒いタンクトップを身にまとった彼らは、一瞬スカル団員のように見える。しかしよく見ると彼らのどこにも、どくろ模様のバンダナやスカル団のマークをかたどったペンダントは見当たらなかった。
プルメリは「おお」と小さく声を出すと親しげな笑みを浮かべ、彼らの方へ歩み寄った。
「待ってたよ。よく来てくれたね。」
「姉さん、あたしの帽子、似合ってますか!?」
「ああ。いいのを選んだじゃないか。」
「姉御! おれはスカルスカーフの代わりに、この真っ白なスカーフにしたんっす! 真っ白な気持ちでやり直します!」
「うんうん、あんたらしいよ。その気持ちいつまでも忘れずに、しっかりやんな。」
「うっす!」
それから元スカル団員の二人は互いに顔を見合わせうなずくと、プルメリに対してびしっと直立の姿勢を取り、すうっと息を吸いこんだ。
「宣誓!!」
高らかな声が同時に響いた。オアシスの梢から数羽のツツケラが驚いて飛びだした。
「あたしたちはプルメリ姉さんに誓います!」
「人のポケモンを奪ったり、傷つけたり、物を壊したりすることは、もう二度としません!」
「上手くいかないからってすぐに逃げて、他人のせいにすることをやめます!」
「自分のポケモンを大事にして、困難に遭った時はどうすれば一緒に乗り越えられるかを考えます!」
男女の声が交互に言葉を連ねていく。プルメリは二人の剣幕に少し驚いているようだったが、それを黙って受け入れ、誓約の対象になることが自分の役割だと十分に知っていた。エンニュートまでも、じっと目を閉じ彼らの言葉に聞き入っているようだった。
「カイ。」
元スカル団員たちの声が続く中、ハウが寄ってきてささやいた。
「今、プルメリさんも、あの人たちも、すっごくいい顔してる。」
はっとしてカイは、ロトム図鑑を構えた。ロトムも急いでカメラモードを再開した。画面の中にプルメリ、エンニュート、そして元スカル団員の男女が映る。
「あたしたちは、」
「おれたちは、」
「まっさらな気持ちで、島巡りに再挑戦します!!」
彼らの締めの言葉と、シャッター音が重なった。
プルメリは二人のあまりの声量の大きさに少し困ったように、それでもどこか誇らしげに微笑んでいた。
元スカル団員たちの見事な決意表明に、ハウが温かな拍手を送った。彼らは用意していた口上を無事に言い終えてほっとしたのだろう。緊張した面持ちをほどき、照れ臭そうにふにゃっと笑った。それから一拍置いて、カイとロトムを見た。
「今、おれらの写真撮ってたんっすか?」
「ああ、リーリエに送るんだと。ほら、あんたらも覚えてるだろう。エーテルで仕事した時の。」
プルメリがカイたちの代わりに事情を説明してくれた。彼らはエーテルパラダイスでの騒動時、現地にいた者たちだったらしい。当時のことを思い出し、カイたちのことを理解すると、みるみる顔を青くした。
「あん時はすいませんでした!」
「ごめんなさいっ!」
勢いよく二人に向き直ると、頭が地面に着くのではないかと思うくらい深々とお辞儀をした。ちょっと気圧されたカイとハウが、いいよ、反省しているならもう大丈夫、と言うまで彼らは顔を上げようとしなかった。撮った写真を見せて、リーリエにこれを送ることについて尋ねると、快く承諾してくれた。
「それじゃあ、あたしたちは島巡りに出発します。」
「ああ。気を付けて行っといで。」
「はい。姉御もお元気で!」
元スカル団員たちはプルメリに対してもう一度居直ると、頭を下げた。その後、元気よくきびすを返した。
「いってらっしゃーい!」
「カプの加護のあらんことを!」
カイとハウも言葉を贈ると、彼らはこちらを向いて大きく手を振ってくれた。
「いい子たちだろ。」
元団員たちがずいぶん離れてもなお、小さくなったその背中から視線を外さないまま、プルメリがつぶやいた。
「あたいはさ、自分たちがやらかしたこと、しっかりけじめつけなきゃいけないと思ってる。申し訳なさもある。だけど、それでも、スカル団がなかったほうが良かったとは、一度だって感じたことはないよ。グズマは確かにどうしようもない男だったけど、グズマのおかげで、一時的にでも救われたやつは多かった。スカル団は、あるべきだったんだ。」
その言葉にカイもハウも、素直には同意できなかった。なぜなら島巡りの中で、スカル団に傷つけられた人やポケモンたちの怒りや悲しみを、たくさん見てきたからだ。けれど他ならぬその島巡りという因習の存在が、どこかでゆがみを生み、スカル団がその受け皿になっていたことも分かり始めていた。だから同意できないからと言って、プルメリの言葉を簡単に否定することもまた、できなかった。
カイとハウとプルメリは、しばらくそうして黙ったまま、新しい未来を選んだ若者たちの向かった先を、見つめ続けていた。