Fall in LOVE
第1話 第2話 第3話 第4話 第5話 第6話
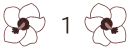 「はー、今日のバトルツリーも楽しかったなー!」
「はー、今日のバトルツリーも楽しかったなー!」
ポニ島にそびえる巨木を利用して造られた施設を背中にして、ハウは満足そうな声を上げた。そうだね、と隣を歩くカイも同意する。
「まさかここでカキくんに会えるなんてね。」
「すごい偶然だったねー。でもカキ強すぎだよー。ファイアロー速すぎー!」
「炎ポケモン以外の扱いも上手だったね。ガルーラを育てていたとは知らなかった。」
「しかもメガシンカまで使いこなしてたしー。」
「猛烈な親子愛でしたね……。」
「ねー。次は絶対に勝つぞー!」
それからハウは、この時の技がすごかったとか、あのポケモンは初めて見たとか、興奮冷めやらぬ感想会を続けた。カイはそのひとつひとつにうなずき相づちを打った。
ハウは近ごろ他地方のポケモンに興味津々だ。ガラルのアーマーガアタクシーのこととか、ジョウトの灯台に住んでいるポケモンについてとか、楽しそうに話すのをカイはもう何度も聞いている。異国のポケモンたちを実際に見てみたいという思いが、彼の足をバトルツリーに向かわせるのだろう。様々な地方からトレーナーが集まるバトルツリーは、2人のお気に入りデートスポットだった。
「だけど今日はイッシュのポケモンあんまり見なかったなー。残念。」
「ハウさん、会いたいポケモンがいるの?」
「うん! オノノクスでしょー、サザンドラでしょー、あとクリムガンも!」
ドラゴンタイプばっかりだね、とよくよく話を聞けば、先日読んだ雑誌にイッシュ地方のチャンピオン、アイリスへのインタビュー記事が載っていたそうだ。見たこともない屈強なドラゴンポケモンたちが、自分よりも幼い少女を囲みたたずんでいる写真がとても印象的だったらしい。
「バトルツリーならイッシュのドラゴンポケモンにも会えるかと思ったけど、そう都合よくはいかないなー。」
「そんなに興味があるなら、待ってるだけじゃなくて行ってみたらいいんじゃない、イッシュ地方に。」
カイの発言にハウはちょっと目を大きくする。その瞳の奥が好奇心にきらりと光るのを、カイは見た。しかしわずかにうつむいたハウが再び視線を戻した時、彼はハラの門下生の顔になっていた。
「いや……おれはまだまだ。もっとじーちゃんから学ばなきゃいけないことあるし、タッパとラップのこともあるし。」
タッパとラップは、ハウが面倒を見ているスカル団員したっぱの男性たちの名前だ。そんな答えが返ってくる気はしていた。カイ自身は他地方への旅行についてとても興味があるのだが……今はまだそれを主張する時ではないのだろう。
「でもでもー、行ってみたくないわけじゃないからね! グズマさんも戻ってきたし、タッパとラップはたぶんもう大丈夫だからー。」
カイの胸中を察したのか、ハウは急いで付け加えた。
ずっと行方不明だったグズマは、前触れなく現れた。カイにポケモンバトルを仕掛けるなどひと騒動あった後、駆けつけたハラに連行され、現在はリリィタウンで「鍛え直し」の最中だ。
ならず者集団の元ボスの唐突な参入に、ハラの道場は未だざわつきの収まらない雰囲気だが、一方でタッパとラップは「グズマさんが一緒なら!」とより一層鍛練に身を入れているそうだ。
きっといい方向に行くと思う、というのがハウの感想だった。
「だからカイも今度見学においでよ。アローラ相撲してるグズマさんに会えるかもー。」
にっと歯を見せるハウに、カイも「それは楽しみ」と微笑んだ。
グズマがいなくなった。
そう聞いたのは、ほんの数日後のことだった。
その日、カイはトロピウスのハウレを連れてリリィタウンを訪れた。たくさん収穫したトロピウスのふさを、ハウたちに届けるためだ。
ハウレはカイがアローラに引っ越しする前から一緒にいるポケモンだが、こちらに来てからは気候が合うのか大変調子が良い。どんどん実る首のふさのおすそわけ……というより消費を手伝ってもらうのを、ハウにお願いしたというわけだった。
出迎えてくれたハウは、トロピウスの背中に乗ったたくさんの袋を見て歓声を上げた。
「これ全部トロピウスのふさー!? 本当にすごい量だなー。これだけあれば、お弟子さんたちみんなに行き渡るよ。ありがとう、カイ、ハウレ!」
 ハウレはひと声鳴き、ご機嫌で
ハウレはひと声鳴き、ご機嫌で
トロピウスはアローラには生息していないポケモンだ。物珍しい差し入れに、ハラの門下生たちはすぐに集まってきた。袋を運んだり、さっそくふさを食べて感想を述べあったり、おそるおそるトロピウスの体に触ってみたり、一同めいめいにはしゃいでいる。
ハウもふさを口にして、「あまーい!」とご満悦だった。
にこにこと彼らを眺めていたカイは、しばらくして「あれ?」と辺りを見回した。
「グズマさんは? それに、タッパくんとラップくんも。」
ハウは明らかに言葉を詰まらせた。はばかるような内容なのだろうか。カイが首をかしげて待っていると、
「グズマなら逃げたぜ。」
門下生の青年が寄ってきて、先に答えた。
「今朝のことだ。俺たちが起きた頃にはもう、もぬけの殻だった。」
驚いてカイはハウの顔を見る。ハウは目を伏せながらもうなずいて、兄弟子の証言を事実だと認めた。
「みんなで探したんだけどー、グズマさん、どこにもいなくて……。」
「で、タッパとラップはまだグズマを探してるってわけ。無駄だっつってんのに、ハラさんもなんで好きにさせてるんだか……。」
別の門下生が会話に加わった。ほんとほんと、と先の青年が相づちを打つ。
「グズマなんて帰ってきたってしょうがないのにな。」
「いっそグズマを見つけて、あいつらも出ていけばいいんだよ。結局、半端もんのスカル団なんだから。」
「ははは! その通りだな!」
彼らの下品な笑い声を、「あのさー」と切り裂いたのは、ハウだった。
「そういう言い方って、良くないと思う。」
ハウの隣にいるカイにはよく見えた。彼の瞳に燃えている怒りも、兄弟子たちにたった1人で反論して震える小さな肩も。
もしかすると門下生たちは、ハウの静かながらも決然とした言葉に、鬼の片鱗を感じたのかもしれない。「じょ、冗談だよハウくん……」とか「ちょっと言い過ぎたな。ごめんごめん」とか、きまり悪そうにつぶやいた。
ハウは彼らには答えず、「あっちで食べよう」とカイの手をつかむと、返事も待たずに歩きだした。トロピウスものっしのっしと2人を追った。
ひとけの少ない町の外れで、ハウはようやく足を止めた。それからひとつ息を吐き、くるりとカイを振り返る。
「いきなり引っぱっちゃってー、ごめんねー?」
「ううん。気にしてないよ、ハウさん。それに、ここで食べるほうが眺めいいよね!」
そう言ってカイは木陰に座った。
ここが特別見晴らしの良いスポットではないことは、2人とも知っていた。ハウは眉を下げた笑みを小さく浮かべ、カイの隣に腰かけた。
しばらく黙ってふさを口にする2人に、トロピウスがそっと顔を寄せてきた。しきりに喉元をアピールしている。きっと「もっと食べれば元気出るよ」とでも伝えたいのだろう。
カイは「ありがとう、ハウレ」と2人分をもぎ取り、ハウにもその心遣いを手渡した。ハウはにこりと笑ってトロピウスに感謝を示した。
「タッパくんとラップくん、心配だね。」
カイが言った。
うん、とハウは答える。
「すげーショック受けてた。」
「2人ともグズマさんのこと大好きだもんね。」
「昨日まで楽しそうに話してたから、余計にさー。置いて行かれたって感じてるみたい。そりゃそうだよねー。黙って行っちゃうなんて……。」
ハウの言葉は最後まで続かなかった。リーリエを見送った時のことを思い出したのかもしれない。カイはそっとハウに近づいて、手を重ねた。ハウはカイを見て、月明かりのように微笑んだ。それから、深いため息をつく。
「なのにおれ、タッパとけんかしちゃったんだ。」
その先をどう説明すればよいか、ハウはなかなか決められなかった。それでもカイがじっと沈黙に耳を傾けてくれているので、ハウはようよう口を開いた。
「タッパとラップがあんまりしょげてるから、おれ、言ったんだ。『おれは置いて行かない。おれはここにいるから』って。そしたら、タッパにめちゃくちゃ怒られたー……。」
「タッパくんは、何て?」
「『ふざけんな、おまえにグズマさんの代わりができるっていうのかよ!』って。おれ、とっさに謝ることもできなくて、タッパは怒って行っちゃった。おれ、タッパたちにひどいこと言った……。」
大事な人が遠くへ去ってしまう痛みを、ハウはよく知っている。寄り添おうとしたのが裏目に出たのだろう。
ぐずぐずと重力だけではない要因で沈んでいくハウの頭を、カイは優しくなでてあげた。さらにトロピウスが翼を広げ、そんな2人をまとめて葉陰に包みこんだ。アローラにいる誰もに等しく流れる時間を、風が静かに運んでいく。
「タスカル団は、今はそっとしておいたほうがいいかもね。」
「うん……。」
「グズマさんも、たぶん心配いらないよ。グズマさんなりの考えがあるからこそ飛びだして行ったんだろうし。」
「うん……。」
よしよしと愛撫を重ね、トロピウスを見上げて微笑みながらカイは、しばらくアローラから離れることはなさそうだなと思った。ハウはきっとタスカル団を放ってはおかないし、そんなハウを置いて1人で旅立つのは気が引ける。それにカイ自身、アローラリーグ初代チャンピオンとしての務めがあるし。
旅行のことは、彼らが落ち着いてからゆっくり計画しても遅くないだろう。そう考えながらカイは、ハウの髪の中で指を遊ばせていた。
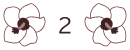 ところが、カイの考えを大きく揺るがす事件が起きる。
ところが、カイの考えを大きく揺るがす事件が起きる。
次の日もカイはトロピウスのふさを袋いっぱいに詰めて、リリィタウンを訪れていた。ふさはまだまだ余っていた。たくさん消費するためにミックスジュースを作ろうとかフルーツケーキがいいとか、2人で意見を交わしていた時のことだ。
空に裂け目が現れた。
ウルトラホールだ。島巡りで何度かその現象を見ていたハウとカイにはすぐ分かった。
しかも出現場所はリリィタウンの近く。今にもウルトラビーストが町を襲いに来るかもしれない。
「行こう、カイ。」
2人は顔を見合わせてうなずくと、手近な町人にハラを呼んでくるよう依頼し、ウルトラホールを目指して走り始めた。
悪い予想は的中するもので、ハウとカイはリリィタウンを出てしばらくもしないうちに、ウツロイドと遭遇した。それは上空をふよふよと浮遊しながらこちらに向かってくる――つまりリリィタウンの方角へ進んでいる。
カイはルガルガンを、ハウはネッコアラをボールから出し、慎重にウツロイドの動きを観察した。興奮はしていないようだが、ホールに戻る気配もない。どうするべきか……判断しあぐねている間に、ウツロイドがカイに狙いを定めて突進してきた!
「ケケンカニ、ストーンエッジ!」
その時、背後から響いたのは頼もしい男性の声。しまキングのハラが加勢に現れた。ウツロイドは鋭い岩槍に阻まれて動きを止める。
「2人ともご無事ですかな!」
「じーちゃん!」
「はい! ありがとうございます!」
カイ、ハウ、ハラとポケモンたちは、並び立ってウツロイドに相対した。
ウツロイドが半透明の触手を振り上げ、岩雪崩を召喚した。
カイのルガルガンとハウのネッコアラは、それぞれのトレーナーのかけ声に合わせて、流れるように襲いくる岩の猛攻を巧みに避けた。
ハラのケケンカニは回避を選ばず、正面から岩雪崩を受け止めた。すかさずハウのネッコアラがその不動の体を踏み台にして大ジャンプ。一気にウツロイドに迫った。
「ウッドハンマー!」
ハウの指示を受け、巨大なハンマーと化したネッコアラの枕木がウツロイドを撃ちぬき、体勢を大きく崩した。
「よし、いいよーネッコアラ!」
称賛の声をかけながらハウは、攻撃の反動でバランスを失ったまま落ちるネッコアラを抱きとめに走った。しかしウツロイドもただでは倒れない。ふらつきながらも、ネッコアラめがけて毒液を吐きだした。
「ハウさん!」「危ない!」
カイとハラが同時に叫ぶ。
ハウはネッコアラをキャッチすると腹に抱えこみ、身を縮めた。直後、ハウの上に毒液が降り注ぐ。
「ハウ!!」
カイの悲鳴に、
「お、おれもネッコアラも大丈夫ー! それより今のうちにビーストを! 町に行っちゃう前に!」
大声で答えが返ってきた。あの声量が出るなら、とりあえずは無事か。カイはウツロイドに視線を移した。
ウツロイドは空中で体勢を立て直しつつあった。ハウとネッコアラが作ってくれたチャンスを無駄にするわけにはいかない。
「ロンウル、岩雪崩!」
カイの指示に、ルガルガンが大きく吠えて答えた。さっき雪崩れたのとは逆方向に、無数の岩塊が暴れ飛ぶ。その激流に耐える力は、もはやウツロイドには残っていなかった。吹き飛ばされたウツロイドは、ウルトラホールに吸いこまれ、姿を消した。
やがて裂け目自体も見えなくなり、空が平時の青色を取り戻した。脅威は去った。
「ハウさん! 大丈夫!?」
ホールの消失を確認したカイは、ルガルガンと共にハウに駆け寄った。
ハラがハウの側に屈みこんで、毒液に触れたのだろうハウの腕に水をかけていた。
「っつ……。」
地面に腰を下ろしたハウは小さなうめき声をあげていたが、カイに顔を向けたとたん、へらりと笑みを作る。
「うん、平気ー。カイもルガルガンも、お疲れ様ー。」
カイは何も言えずにうなずいて、自分のバッグから水入りのペットボトルをあるだけ取り出し、ハラの隣に置くので精一杯だった。
ハラは感謝の言葉を述べて、ハウの患部の洗浄を続けた。
「毒液が左腕に直撃しましたな。一刻も早くリリィタウンに戻りましょう。カイとポケモンたちも、我が家で休んでいきなされ。」
リリィタウンに到着した後、ハラは一服もそこそこに島内の見回りに出かけた。万が一にもウルトラビーストが残っていないか確認するためだ。
カイはハウの母と共に、ハウの手当てを引き受けていた。といっても、傷口の洗浄や救急箱の準備をてきぱきと進めるハウの母の手つきを、カイはほとんど見ているだけだったが。
「ごめんなさい、私、何もできなくて……。」
しおしおと箱から消毒液を差し出すカイに、「なに言ってるの」とハウの母はおかしそうに答える。
「しまキングと一緒に戦ってくれたんでしょう? カイちゃんが力を貸してくれたから、これぐらいで済んだってこと。」
「そうそう。それにー、おれのけが全然たいしたことないからー。」
ハウも微笑む。
それでカイも笑みを返したが、その涙色を悟られる前にうつむいた。
「カイちゃん、疲れてるなら休んでてくれていいからね。キッチンの冷蔵庫に入ってるジュース、どれでも好きなの飲んで。」
ハウの母が気遣ってくれた。
ありがとうございますとカイは礼だけ言って、ジュースを取りには行かなかった。考え事をしていたからだ。
(ウツロイドは間違いなく私を狙っていた……。私が、
カイはウルトラホールを通ったことのある人間――国際警察によって秘密裏に Fall と呼ばれる存在だった。Fall にはウルトラビーストを惹き付ける特性がある。国際警察と共に一件を落着させ、しばらくビーストは現れないと思い込んでいたから、カイは今までそのことを意識していなかった。けれど今後も空に裂け目が生じるというのなら、話は変わる。
カイがいたからウツロイドは町に向かって進み、ハウはそれを止めようとして体を張った。誰が悪いという話ではない。それでも、
(もしも私がここにいなければ、ハウさんはけがをせずに済んだ……?)
そう思わずにはいられなかった。
カイは静かに拳を握った。
幸いハウは軽傷だった。
傷跡のほとんど残っていない左腕の写真をメールに添付して見せてくれたから、まあ信じていいだろう。
ウツロイドがメレメレ島に現れた日以来、カイはバトルツリーデートどころか、リリィタウンの訪問さえしていなかった。何度かハウからお誘いは来たが、その度に「リーグの挑戦者が続いてて……」とか「ポケモンの調子が良くなくて……」とか、ぎりぎりうそではない答えを返していた。
ウルトラビーストの襲撃を恐れていたから、というのがひとつの理由だ。エーテル財団のビッケにはすでに相談していた。いわく、今回のウルトラホールは先の国際警察の件とは別系列の可能性があり、調査結果が出るまでは警戒しておいてほしいとのこと。しばらくはメレメレ島に駐在する財団職員の数も増やしてくれるそうだ。
もうひとつの理由は、アローラを出ることについて1人でじっくりと考えたかったから。自分が Fall である限り、ビーストが現れた時に周りの人たちを危険にさらすのは避けられない。だったら Fall のほとぼりが冷めるまで、アローラから離れるのはどうだろう。ウルトラビーストの出現例がない他の地方なら、Fall であっても比較的リスクは低いはずだ。
「ね。どう思う、ロンウルちゃん?」
ある日の夜、自室でルガルガンをブラッシングしながらカイはつぶやいた。カーペットの上に寝転がったルガルガンは、のんびりあくびをして気持ち良さそうだ。
アローラを出る、とカイは再度音にして言ってみる。
「ハウさんと離れ離れになっちゃうのは嫌だなあ……。でも私がアローラにいることでハウさんが傷つくのは、もっと嫌。」
好きだからこそ隣にいられない。恋慕に落ちた Fall の、悲しい宿命だった。
「はあぁ……。」
カイが長く大きなため息をついた時、ルガルガンが身を起こし、カイの頬をぺろんとなめた。
「慰めてくれるの、ロンウル? ありがとう。」
ルガルガンはがるるっと元気に吠えた。威勢のいい声だ。そう、どんな危険がやって来ても、世界のどこに行こうとも、カイの側にはポケモンがいてくれる。
頼もしい相棒の姿を見て、カイはついに心を決めた。
Fall のほとぼりが冷めるまで、アローラを出て世界中を旅しよう。
それは後ろ向きな気持ちばかりではない。もともと他の地方を訪れることについてカイは強い興味を持っていた。世界のどこかにいる、まだ見ぬ人やポケモンたちに会ってみたい。その希望は熱く輝く光となって、カイをアローラの外に手招いていた。
きっとハウもバトルツリーを登りながら他地方への憧れを話す時、こんな気持ちだったのだろう。けれどハウにとって、今はまだアローラを離れる時期ではない。ならばやはり、1人で行くしかない。
ハウと共に世界中を旅できたら、どんなに素敵だろうか。
カイはその思いを分厚い氷に閉じ込めて、ぐっと心の奥底に沈めた。
そして気持ちが揺らがないうちにパソコンを開き、ハウに会いたい旨をメールした。数分もしないうちに、快諾の返信が来る。もしかしたらハウもカイにメールを送ろうとしていたところだったのかもしれない。
メールには、明日はハウが道場の面倒を見る予定であることが書かれていた。ハラが朝一番でポニ島に出かけるらしい。午後には帰ってくるので、昼食後くらいならゆっくり会えそうとのことだった。
アローラを発つとハウに伝えるのが、辛くないといえばうそになる。けれど心に決めたからには、ハウさんにこそ真っ先に。ちゃんと対面して真っ直ぐに目を見て。
カイはその日、思ったよりは整った気持ちでベッドに入れた。
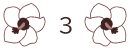 翌朝、空には爽やかな青が広がっていた。
翌朝、空には爽やかな青が広がっていた。
「今日はトロピカルナッツパイを作るわよ! いいレシピが手に入ったから。」
ダイニングに顔を出しておはようの挨拶をしたら、ママがずいぶん張り切っていた。キッチンにはすでにトロピウスのふさやら粉袋やらきのみやら、様々な製菓材料と道具が所狭しと並んでいる。
「カイ、今日のおでかけの予定は?」
「リリィタウンに行こうかなって……。お手伝い、要りそう?」
「ううん、大丈夫よ! あ、でもよかったらハウレちゃんをお借りしてもいいかしら? トロピウスの甘い香りがあれば、より風味良く仕上がるんだって。」
そこでカイはトロピウスを庭に出して、ママを手伝うようお願いした。役目がもらえて嬉しいらしく、トロピウスはいつもの倍くらい翼をばさばさと上下させていた。
あちこち行き来してパイ作りの準備を進めるママと、ママの説明を聞いてふんふんとうなずいているトロピウスを眺めながら、カイはシリアルとフルーツの簡単な朝食を済ませた。なんだか家にいても落ち着かなさそうだ。それでカイは少し早いと知りつつも、身支度を終えたらすぐにリリィタウンへ向かった。ハウに会いたい気持ちが先走っていたのもある。
(ハウさん、今日はハラさんの代わりに道場の面倒見るって言ってたな。ふふ、どんな道場主さんの顔してるんだろ。タッパくんとラップくんは大丈夫かな……。)
思いを巡らせながらリリィタウンに到着した頃だった。
空に裂け目が現れた。
カイは息をのみ、足を止める。
ハラさんに知らせなきゃ、と反射的に考えた。だがしまキングのハラは今、ポニ島に出向中でメレメレ島にいない。
カイはもう一度ウルトラホールを観察した。あれは戦の遺跡のあたりか。光は強い。ウルトラビーストが出てきたら、きっと Fall を目指してリリィタウンにやってくるだろう。もうすぐ近くまでビーストが来ている可能性だってある。
迷っている時間はなかった。ビーストが人里で暴れる前に。また誰かが、カイの大切な人が傷ついてしまう前に。
「私が……なんとかする。ロンウルちゃん、手伝ってくれる?」
じっとりと汗のにじむカイの手の中で、ルガルガンのボールが揺れて答えた。頼もしい振動に自らの鼓動を重ねて心を落ち着かせたあと、カイは急いで町中を走った。
ハウさんに会いませんように、と祈る。会えばきっとハウは自分も戦うと言って付いてくるだろう。それでは意味がない。人目はなるべく避けたかった。
ところが。
「あ、チャンピオン。」
「アローラっス!」
なんとか広場を抜け、ほどなくマハロ山道という所で、見知った顔が現れた。
「タッパくん、ラップくん……ア、アローラ!」
よかった、けっこう元気そうだ。安堵と同時に、この場所にいる理由を問われるだろうと思い、カイはひやりとする。
ところが「わりぃけどハウなら後にしやがれよ」と、タッパがカイの目的を勝手に推測してくれた。
「ハウは今からおれらに用があんだ。」
「いやまあおれらが話しに行くんスけど。」
「同じことだろーが! とにかくそういうわけだから、順番待ち! だぜ。」
強く念を押すタッパに、カイはあっさりとうなずいた。
「わかった。2人ともごゆっくり!」
そうして山頂を目指して小走りに去っていく。
タッパとラップは拍子抜けした様子で、カイの背中に問いかけた。
「え。ハウに会いに来たんじゃないんっスカ?」
「おい、どこ行くんだよ!」
カイは振り返り、少し眉を下げながら笑って答えた。
「えと……ちょっとカプの遺跡へお参りに。ハウさんには待っててねって伝えてください。約束通り午後に行くから、絶対、待っててねって。」
そしてカイは逃げるように2人の前から姿を消した。
タスカル団たちは想定外の反応に、ぽかんとしていた。
「なんなんだよ、あいつ……。いつもハウと一緒にいるくせに。」
「あれ、でも最近は見かけてなくないっスカ?」
「さあな。覚えてねーよ。」
タッパたちは肩をすくめた後、まあこっちの用事をさっさと終わらせちまおうぜと、道を歩いていった。
ウルトラホールが開くのは予想以上に早かった。カイがつり橋の向こうに戦の遺跡の入口を見た時にはもう異世界の色が空にちらつき、1体のウツロイドが宙に漂っていた。さらに2体目、3体目も穴からするりとはい出てくる。
カイはルガルガンの入ったモンスターボールを手に取り、静かに解放した。ルガルガンはすでに承知の意気で、ぐるると低いうなり声を上げている。
橋の下を流れる川の音に負けないよう、カイはウツロイドたちに叫んだ。
「ここには何もないよ! ウルトラホールに帰ってください!」
ウツロイドに目らしい器官はない。けれどカイの言葉に反応して、ウツロイドたちがぎろりと視線を向けたのが分かった。Fall を認識したのだろう。3体とも一様に、ふわりとカイを目指してゆらいだ。話は通じなさそうだ。ならば丁重に帰り道をお教えせねばなるまい。
「……ロンウル、行くよ。ストーンエッジ!」
速攻で終わらせる。カイの意志はルガルガンの力となり、いくつもの岩塊として具現した。ルガルガンの吠え声と共に、鋭く尖った岩の群れがウツロイドたちに襲いかかる。
しかし、まとめて片付けようとする焦りが出た。岩槍の初撃は1体にクリーンヒットしウルトラホールにねじ込んだが、残りは破片がかすった程度で、戦闘を終わらせるには至らなかった。
(やっぱりまとめては無理か……。ここはもう1回ストーンエッジで、1体ずつ確実にホールに押し戻そう。)
カイがルガルガンに次の指示を伝えようとした時だった。
ピリッと空気のしびれるような感覚が肌を刺した。足元を電気が駆け巡る。カイは知っている。これはメレメレ島の守り神が作り出すエレキフィールド。
カプ・コケコが戦の遺跡の上空に現れた。神の鋭い雄叫びが辺りに響き渡り、直後、その体がまばゆく輝いた。すさまじい電撃が放たれる。1体のウツロイドがばちりと弾けてホールの中に消えた。
自分たちだけでなんとかするつもりだったのにという自責は、カプ・コケコが来てくれたという心強さで吹き飛んだ。やはり島の守り神には敵わない。
「ありがとう、カプ・コケコ!」
カプ・コケコはちらっとカイに目線を寄越しただけで、すぐに残り1体のウツロイドを見据えた。礼ならこれを片付けてからだと言っているようだった。
最後のウツロイドは攻撃の意思をあらわにし、ベノムショックを繰り出してカプ・コケコに反撃した。効果抜群の毒液がカプに降りかかるのを見て、カイの脳裏にネッコアラを抱え込んだハウの姿がフラッシュバックする。
「カプゥーコッコッコ!」
一瞬立ち尽くしたカイの鼓膜を、カプ・コケコの甲高い声が震わせた。それは負傷による悲鳴というより、ルガルガンの指揮者に対する発破だった。
ルガルガンがカイの指示を待っている。
ハウが受けた痛みを、また誰かが味わわないためにも。今はひるんでいる場合じゃない。
カイはすうっと深く息を吸いこんだ。
「ロンウル、アクセルロック! ストーンエッジの狙いを付けやすい場所に移動して!」
ルガルガンがひと声鳴き、カイの指示通り飛びだした。ストーンエッジは威力が高い分、的確な発動には精度が要求される。ポケモンも、そしてトレーナーも、有利な位置を取らなければならない。ルガルガンがしっかりと足場を踏みしめたことを確認して、カイも全体が見渡せるつり橋の上へ走った。板1枚はさんだ下で、水の流れる音がする。
よし、このままロンウルがウツロイドを正面に捉えたところで、ストーンエッジを指示――
「カイ!」
カイの思考は、その場にいないはずの人間の声によって中断された。
「ハウ……!」
マハロ山道を登りきった場所で、ハウがライチュウを従え、肩で息をしていた。全速力で駆けて来たのだろう。表情は遠くてよく分からない。ただじっとカイを見つめ、何かを言おうとして迷った後、こぼれかけた言葉を押しこむように叫びながらこちらに向かってきた。
「おれはカプ・コケコを手伝う! カイは」
しかしハウの声は途中でウツロイドの咆哮にかき消された。頭上でカプ・コケコとウツロイドが激しくもつれあっている。ばちんと光が弾け、いきりたったウツロイドがやたらめったら岩を発射した。落ちてくる岩が、地上にいるルガルガンや、カイの足元にも襲いかかる。
カイが「あっ」と思った時にはもう、木板がばきりと音を立てていた。大きく足場が揺れた後、カイは逃れられない重力の支配下にあることを、ぐらりと理解した。
つり橋が落ちる。
「カイーーーーーーっ!!!!」
遠ざかっていく空の中に、人影が躍りでた。それはこちらに向かっていっぱいに手を伸ばし、必死の形相で、落ちるカイを追いかけてきた。
ハウがカイを助けるため、崖から飛び降りた!
ハウの手がカイの腕を捕まえたのと、岩やつり橋の破片が川に落ちて背中で水しぶきを上げたのと、突然反重力の力にぐんと引っ張られ落下が止まったのとが、ほとんど同時だった。
カイとハウと周辺のがれきが、空中でぴたりと静止していた。頭の後ろで川の音がざあざあ聞こえるので、時間が止まったわけでも死んでしまったわけでもないと、なんとか判断できた。
ハウを追いかけてきたライチュウがサイコキネシスを発動し、間一髪で落下を阻止していた。
ライチュウは2人を谷底の小さな岸辺に運んでくれた。硬い地面に足をつけて、サイコパワーの補助から解放されてもなお、カイは体がぐらぐらふわふわと揺れているような心地がした。カイが上下を間違えず立っていられたのは、空中でつないだ手を一瞬たりとも離そうとしないハウが、隣にいてくれたからだった。
「カイ、けがはない?」
「ハウさん、大丈夫?」
互いの無事を確認する言葉が重なった。2人はそれぞれにうなずき、ハウはカイの手をぎゅっと握り直して「よかったぁ……」と大きく息を吐き頭を垂れた。
「ハウさん、あの……助けてくれてありがとう。」
感謝を述べても、ハウはゆるゆると首を動かすばかりだった。それが肯定なのか否定なのかは、カイには読み取れなかった。
ライチュウが2人の側に飛んできて、心配そうに鳴いた。ハウはようやく顔を上げて相棒に答える。
「おれもカイも無事だよー。ありがとう、ライチュウー。」
谷底から空を見上げると、ウルトラホールの裂け目が消えつつあった。地面を走る電流も収まっている。どうやら最後のウツロイドは、カプ・コケコかルガルガンが片を付けてくれたようだ。
「そうだ、ロンウルちゃん……大丈夫かな。心配してるかも。」
「そうだね。ライチュウ! カイのルガルガンを探して、おれたちは無事だって伝えてきてくれる? その後で登るの手伝ってくれたらいいからー。」
ライチュウは承知のひと声を上げると、飛んでいった。谷底には、手をつないだまま立ち尽くすカイとハウと、谷川を流れる水音だけが残された。ざあざあとうるさい沈黙の後、先に口を開いたのはハウだった。
「なんで、1人で来たの。」
ハウはライチュウを見送った姿勢のまま、カイと目を合わせようとしなかった。声は怒っているのか、悲しんでいるのか、戸惑っているのか、少し震えていた。
「ウルトラホールの出現に気付いて、じーちゃんの代わりになんとかしようって、思ってくれたんだよね。そりゃあおれもさ、カイとカイのポケモンたちが強いのはよく知ってるし、疑ってもないよ。だけどー……おれってそんなに頼りにならない?」
「違う、ハウさん、そうじゃなくて」
ハウが振り向き、カイは思わず言葉を詰まらせた。こちらを見つめるハウの黒く大きな瞳は、潤んでいた。
その表情を直視できずカイはうつむき、そうじゃなくて、と繰り返した。
「また誰かが傷付くのが嫌なの。また、大切な人が……ハウさんが痛い思いをしたらどうしようって。」
「だからー、おれのこと信用してないでしょ。おれやライチュウたちだって鍛えてるんだよ。ちょっとやそっとじゃ、やられたりしないからさー。もっとおれのこと頼って」
「違うんだよ、ハウさん。」
カイの強い語気に、ハウはただならぬ気配を感じ、口をつぐんだ。
「ちょっとやそっとなんて話じゃないんだよ。私は、ウルトラビーストを呼んでしまう。私がいると、みんなを危険に巻きこんじゃう。私は……そういう性質になっちゃったんだって。」
「……ど、どういうことー?」
それでカイは、Fall についてハウに打ち明けた。情報はエーテル財団を通じて得たと説明し、その名称や国際警察が関わっている部分については伏せておいた。
ハウは少なからず驚いたようだった。それからぎゅっと眉根を寄せ、そういうことだったんだ……とつぶやいた。
「じーちゃんと一緒にビーストを退治した日から、なんかいつもと様子が違う気がしてたよ。カイ……ひとりで抱えさせちゃって、ごめん。」
ハウさんは何も悪くない、とカイは首を振る。
「それに心配いらないよ。この性質はにおいみたいなものらしいから、時間が経てばなくなると思う。だからそれまでの間、私、アローラを出るつもりなんだ。」
はっとしてハウはカイを見た。絶句という語が表情になれば、こんな色になるのだろう。何も言えないハウに対して、カイもまた、言葉を継ぐのに勇気が要った。
結局、ハウに痛い思いをさせているのは私自身だ。わかっていた。もう、ここで終わりにしなきゃ。
ひとつ呼吸を整えて、カイはハウの視線にあえて笑みを向ける。
「でも前向きな気持ちのほうが大きいよ! 他の地方に行くのって面白そうだし。今日は、それをハウさんに誰よりも早く伝えたくて」
「嫌だ。」
ハウの声は予想以上に芯が通っていて、真っ直ぐだった。
悲しませるとは思っていた。けれどカイは心のどこかで、ハウなら見送ってくれるだろうと高をくくっていた。カイの話を途中でさえぎってまで自らの主張を発したハウの目には、悲哀どころか、決然とした覚悟の色が見てとれた。
「おれは、カイと離れたくない。カイがアローラを出るなら、おれも一緒に行く。」
「ハウさん……でも」
続く言葉をカイは返せなかった。突然、ハウがカイを思いっきり抱き寄せたからだった。
「カイ……カイ。」
ハウの温かな胸の中で、カイは彼の震える声を聞いた。
「どこにも行かないで、カイ。ビーストを呼んだって構わない。おれの隣にいて。」
ぎゅうっとハウの腕に力が入る。決して離さないように力強く、けれど決して壊さないようにやわらかく、ハウはカイを抱きしめた。
「……怖かった。初めて本気で、カイを失うかもしれないと思った。」
ハウはカイがそこに存在することを、体全部で感じるように、ゆっくりと背をなでた。カイもそれに応じて、ハウの背中に腕を回した。
「おれ、大好きな人が側にいない気持ち、知ってるつもりでいた。でも全然違った。もっと暗くて、寒くて、ぐちゃぐちゃで……。カイがいなくなったら、おれは……。カイ……」
カイを抱く腕に、ハウが再び力を込める。
「おれ、きみを、愛してる。」
カイの体が熱いのは、きっとぴったりくっついているハウから体温を分けてもらっているからだと思う。どくんどくんと脈打つ音が、自分の内側で響いているのか、ハウから聞こえてくるものなのか、判別できなかった。けれどその交わりは不思議と心地良い。カイは目を閉じ、耳を澄ませ、2つの鼓動が溶けあうのを感じた。
「私も、あなたを、愛しています。」
もうだめだな、とカイは思った。
どんな理屈をくっつけて1人で行こうとしても、魂が「ここがいい」と叫ぶ。ハウの隣でなければだめだ、と。昨夜ルガルガンと共に固めたはずの決意は、春を迎えた氷のように溶けていった。それは透明よりもきれいな輝きとなって、カイの乾きに染みこんだ。
長かったのか短かったのか分からない抱擁の後、カイとハウはゆっくりと顔を上げ、互いを見つめた。不意に、ハウが照れくさそうにふにゃっと微笑んだ。
「おれ、恋に落ちてるんだなあって……きみを失いそうになって、やっと気付いたんだよ。遅くなってごめんね。」
つまり昨日までのハウの愛情表現は、全部無自覚のものだったらしい。そう思うとなんだか可笑しくって、カイもまたふにゃっと口元をゆるめた。
 ライチュウが戻ってきたのは、空の裂け目の残光もすっかり消えた後だった。大きな声でカイとハウに呼びかけながら、ライチュウが上を指している。見れば、壊れたつり橋の端から心配そうに谷底をのぞいているルガルガンの姿があった。
ライチュウが戻ってきたのは、空の裂け目の残光もすっかり消えた後だった。大きな声でカイとハウに呼びかけながら、ライチュウが上を指している。見れば、壊れたつり橋の端から心配そうに谷底をのぞいているルガルガンの姿があった。
「ロンウルちゃーん!」
カイが手を振ると、ルガルガンはおぉーんと歓喜の遠吠えで答えてくれた。良かった、ロンウルは元気そうだ。
ライチュウがサイコパワーを使い、カイたちが崖上まで登るのをサポートしてくれた。途中、カプ・コケコがさえずり、青空の中でぱちっと光って飛び去っていくのを見かけた。たぶんあれがカプなりの挨拶なのだろう。
無事にルガルガンと合流できたカイとハウは、まずはポケモンたちにポケマメなどを与えて労った。それから戻し損ねたウツロイドがいないか念入りに確認し、帰路についた。
「つり橋、また壊れちゃったね……。」
戦の遺跡を振り返り見て、カイは申し訳なさそうにため息をつく。カイがアローラに来たばかりの頃にも一度、橋が落ちてしまったことがあった。やっと修理が終わったところだったのに。
「仕方がないよ。じーちゃんにすぐ教えよう。あっ、でもー。2人で崖の下に落ちたことは、内緒にしておこうなー? いくらカイを助けるためだったとはいえ、飛び降りたなんてバレたら、大目玉くらっちゃうー。」
鬼のハラの形相を想像しているのか、すっぱいきのみを食べた時みたいな顔をするハウを見て、カイはふふと笑みをこぼす。
「2人だけの秘密、だね。かっこよかったよ、ハウさん。」
「へへ……。」
「秘密の共有ついでに、私がウルトラビーストを引き寄せる性質を持っているっていうことも、内緒にしておいてほしいな。余計な心配かけたくないから。」
ハウは少し考えたが、「わかった」と承諾した。
会話はそこでいったん途切れた。しばらくの間ざくざくと山道を下る足音を響かせた後、「おれさ」と話の糸をつなぎ直したのはハウだった。
「タッパたちと、けじめ付けなきゃ。」
カイを追いかける前にタスカル団に会ったと、ハウは話した。その時にカイが1人でウルトラホールの発生場所に向かったことも分かったらしい。「待っててね」という伝言がきちんと伝わっていなかったことをカイは残念に思ったが、いずれにせよハウの行動は変わらなかっただろうから、彼らに非はない。
「話したいことがある、って言われたんだ。それを後回しにしてもらってこっちに来たから……おれ、ちゃんと向き合わないといけない。」
自分の弱さを認める強さを持つのは難しいと、ハウが言ったことがあった。けれど、きっと快くはないだろう場に自ら臨もうとするハウは、十分強いとカイは思う。
「カイはおれん家で待っててよ。今はじーちゃん留守だけど、かーちゃんはいるからさー。」
「いいえ。私も一緒に行きます。」
カイはハウの手首をつかまえ、ちょっと大げさに口をへの字に曲げてみせた。
「隣にいろって言ったの、ハウさんじゃない。」
「あはは……そうだねー。」
ハウは気恥ずかしそうにはにかんで、カイの手を握り返した。
「カイがいてくれれば心強いな。ありがとう。」
「ふふ、どういたしまして。」
そうして2人は互いをしっかりとつないで、リリィタウンに帰還した。
タスカル団を探す手間はほとんどなかった。町に着いてまもなく、タッパとラップの姿が目に入ったからだ。彼らはハウを待っていたらしい。そのくせ変に気まずそうで、こそこそささやきあい、カイたちの方にはなかなか近づいてこなかった。
「タッパ! ラップ!」
結局、ハウが口火を切る。
「さっきはごめん。緊急事態だったんだー。」
「お、おう……。別にかまわねーよ。」
「もう大丈夫なんでスカ?」
「うん、おかげさまでー。それで、話って何?」
タスカル団は答えなかった。
しばらくしてラップがタッパを小突き、発言を促す。それでもタッパが口をつぐんだままなので、ラップはあきらめたように息を吐き、「おれら謝りたいと思ってるんっス」と話し始めた。
「グズマさんがいなくなった日、せっかくハウが心配してくれたのに、タッパがひどい返しして……それからずっと空気悪くしちゃったっスカら。申し訳なかったっス。」
ラップが上半身を深く曲げた。タッパは微動だにしない。さすがのラップも苛立った様子で、相棒の名を呼んだ。
するとタッパは、頭を下げる代わりに右腕をハウに向かって突き出した。その手に握られていたのは、モンスターボール。
「ハウ。今からおれと勝負しやがれ。おまえが勝ったら、土下座してやらあ。」
これには一同驚いた。
真っ先に口をとがらせたのはラップである。
「タッパ、話が違うっス! ちゃんと謝るって言ったじゃないっスカ!」
「るっせーな! これがおれなりのちゃんとだっつーの!」
そんなのヘリクツっス! 口出しすんな、とタスカル団がもめ始める。
けれど2人の言い争いに決着がつく前に、ハウは「いいよ」とよく通る声で答えた。
「ポケモンバトルしよう、タッパ。きみが勝ったら、おれが謝る。」
「お、おう。そうこなくちゃな。」
まだ不服そうなラップを横目に、ハウとタッパは開けた場所に移動した。マハロ山道にほど近いリリィタウンのはずれは人も建物も少なく、ポケモンバトルには好都合だった。
カイとラップは一緒にバトルの行方を見届けることにした。
「おれはタッパの相棒っスけど、」
ラップがぽつぽつとカイに説明してくれる。
「でも、だからこそ、あれはタッパが悪いって思ったから、謝ろうって言ったんっス。タッパだって納得してたのに。本当っスよ……。」
「うん、ありがとうラップくん。けど、ああなっちゃったらハウさんも止まらないだろうし。ポケモンバトルでしか語れないことが、きっとあるんだよ。タッパくんにも、ハウさんにも。見守ってあげよう。」
ラップがうなだれながら、うなずいた。
タッパはパートナーのスリープを繰り出した。
「1対1の1本勝負でどうだ。」
「いいね。望むところー。」
答えてハウが繰り出したのは、イーブイだった。先日タマゴから生まれたばかりのイーブイで、実戦の経験はほとんどないはずだ。
タッパもそれを知っていたから、驚き困惑した。
「おまえ、そのイーブイって……勝つ気あんのか?」
「もちろんだよー。生まれたばかりだからって、油断しないほうがいいよ。技の練習、いっぱいしたもんなー。」
キュルッと元気よく答えるイーブイ。ハウは鋭い目でタッパを見据えた。
「タッパー。まさか、負けるつもりで挑んでないよね?」
「あ……あったりまえだろ。今日こそおまえに勝ってやる! いくぜスリープ、念力!」
「イーブイ、しっぽを振る!」
まるで遊びにでも誘うかのように、ぶんぶんと豪快に尾を動かすイーブイ。スリープはその勢いに少し圧されつつも、得意の念動波を放った。見えない攻撃にばちんと襲われ、イーブイはびっくりしてぴょんぴょこ跳ねている。
「よし、ヒット! いいぞスリープ!」
スリープが誇らしげに吠え、タッパの声に応えた。
タッパとスリープはずいぶん見違えたと、ハウは思う。
島巡りの途中、初めて彼らに会った時、タッパはただ闇雲に技の名前を叫ぶばかりだった。だけど今は違う。それは絆に基づく指示と応答だ。2人の呼吸は、しっかりと合っている。
自分の指導のたまものだ、とは思わない。どころか全然自信がない。ポケモンと息を合わせることについて語り聞かせたこともあったけど、タッパはつまらなさそうにハウから視線をそらすばかりだった。じーちゃんみたいにはいかないなぁと、あの時はそれなりに落ち込んだものだ。
けれどもハウとポケモンの接し方を近くで見て、タッパなりに、無意識にでも、何か感じるところがあったのだとすれば。それが今のタッパとスリープの戦い方に結びついているのだとすれば。
心の奥底から湧きあがる感情を、ハウはイーブイと共に形にし、タッパにぶつける。
「イーブイ、右から電光石火!」
「うおっ、ス、スリープ! ずつきで応戦だ!」
「左にかわして電光石火!」
素早く相手を翻弄するイーブイの動きに、スリープもタッパもなかなか付いてこられない。しかし彼らは一瞬だってあきらめなかった。
「スリープ今だ、毒ガス!」
攻撃を終えたイーブイの隙を狙って、タッパの指示が飛んだ。これはまともに入る。イーブイは初めて経験するガスのにおいに、頭をぐらぐらさせながら驚いているようだ。
「イーブイしっかり! いったん距離を取って!」
陣形は再び戦闘開始時と同じになり、両者にらみ合った。
「タッパとスリープ、ほんとに腕を磨いたよねー。」
ハウが言った。
タッパは答えない。
上出来だった。タッパは今、スリープと共に勝利をもぎ取る道を、必死で探している。言葉を発する余裕なんてないくらいに。
おれとイーブイも、負けてられないな。
ハウはぐっと全身に力を込めて、タッパを見た。タッパもハウを見据えていた。
ここ一番の勝負どころは、相手の目を真っ直ぐに見よ。
ハラのバトルスタイルから、ハウが学んだことだった。
様々な人やポケモンとゼンリョクで交わる時、生み出される何かがある。
同じことをタッパも感じていてくれたら嬉しい。
きっと伝わっていると、信じている。
きっと彼らは、応えてくれる。
ハウと、イーブイと、タッパと、スリープの視線が、一直線に重なった。
 「イーブイ、突進!」
「イーブイ、突進!」
「決めろ! 念力!」
強い波動がイーブイに襲いかかる。イーブイはさらに強い力でその波を押しのけ、加速し、スリープのど真ん中に激しい一撃をたたきこんだ。
2体のポケモンたちは勢い余って一緒に転がり、倒れ伏した。そのまましばらくどちらも地面に張り付いたままだったが、やがてもぞりと毛玉が動いて、イーブイが立ち上がった。スリープは目を回してひっくり返ったままだった。
勝敗は決した。
イーブイが遊び足りないかのように「ルルルーッ」と高く鳴いた。
タッパは黙ったまま、モンスターボールをかざした。放たれた光がスリープを包み、ゼンリョクを出し切ったポケモンを中に収納する。そのボールをタッパはぎゅっと握りしめ、見つめた。それから息を大きく吸いこんで、正座し、ぶつけるほどの勢いで額を地面に付けた。
「ハウ! ひでー態度取って、悪かった!」
場は水を打ったように静まりかえる。
最初に動いたのはイーブイで、ぴょんぴょん駆けていくとタッパを囲うように回り始めた。きゅわーと鳴きながら跳ね、「急にうずくまってどうしたのー?」とでも問うているかのようだ。
ハウはおもむろにタッパのもとに歩み寄り、イーブイを抱きあげた。くすぐったそうに笑うイーブイの健闘を称えて頭をなでてやってから、ハウはタッパへ手を差しだした。
「おれも、ごめん。」
タッパは顔を上げ、しばらくハウの手を見つめていた。少し迷った後、ゆっくりと自分の手のひらを出し、握る代わりにぱちんとたたいて自力で立ちあがった。
見守っていたラップは、ちょっぴり不安そうな表情でカイに尋ねる。
「仲直り……っスカ?」
カイは肩をすくめて微笑んだ。
「たぶん、ね。」
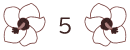 それからカイ、ハウ、タッパ、ラップの4人と、遊び足りないのかボールに戻ろうとしないイーブイの一行は、ハウの家でいったん休憩をとることにした。時刻は正午過ぎ、そろそろお腹も空いてきた。
それからカイ、ハウ、タッパ、ラップの4人と、遊び足りないのかボールに戻ろうとしないイーブイの一行は、ハウの家でいったん休憩をとることにした。時刻は正午過ぎ、そろそろお腹も空いてきた。
玄関扉を開けようとすると、中から人が出てくるところだった。その姿を見とめて、カイの声はひっくり返る。
「あれ、ママ!?」
「あら、カイ! それにハウくんと、お友達の皆さんも! ちょうどよかったわ。トロピカルナッツパイが焼けたから、届けに来たのよ。」
そういえば今日のママの予定はパイ作りだった。わざわざ持ってきてくれたのもさることながら、そのタイミングの良さにカイは我が母ながら舌を巻く。
「たくさんあるから、どうぞ皆さんで召しあがってね。カイ、ハウレちゃんのボールはカイの机の上に置いておくわ。どうもありがとう。ハウレちゃんも大満足だったわよ。」
それじゃごゆっくりー、と手をひらひらさせて帰っていくママを、カイたちは半ばあっけにとられて見送った。
「カイのかーちゃんってー、なんかいろいろ、すごいよねー。」
「恐れ入ります……。」
「じゃあ素敵なお昼ごはんもあるみたいだしー、みんな入って入って。おれ、飲み物とってくるからー。」
そう言ってハウは、一同を広間に招いた。
タスカル団はこのようなもてなしには慣れていないらしい。かばんを下ろしたり手を洗ったりしてくつろぐ準備を進めている間、ずいぶんそわそわしていたが結局、床に座りこんで落ち着いた。カイがソファを勧めたところ、そちらは「スカしてねーからいい」そうだ。まあ広間に置かれているローテーブルは、直座りのほうが使い勝手がいいかもしれない。
イーブイはタッパたちの顔が近くにあるので嬉しいらしく、周りをぴょんぴょこ跳ねまわっていた。
「お待たせー。」
しばらくすると、ハウがモーモーミルクとトロピカルナッツパイを運んできた。そしてタスカル団たちを見てソファに座るよう促したので、タッパは再び床上のスカし具合を伝えることとなった。「2人がいいなら構わないけどー」とハウは苦笑しつつ、テーブルに皿とコップを並べる。
ママお手製のパイからは、トロピウスの甘い香りとバターの風味の溶けあった香気が漂っている。もう1秒だって惜しかった。
「それじゃあ、いただきまーす!」
カイとハウは同時にパイにかぶりついた。
加熱されてとろけたトロピウスの果実の甘味が、さくさくの歯触りの中でほどけていく。カリカリのナッツと生地の中に仕込まれている数種のきのみは、味と食感に変化をもたらす名脇役だ。次はどんな具材に会えるだろうと夢中で頬張っていたら、パイはあっというまに手の中から消えてしまった。
「おいしーい! さすがカイのかーちゃん!」
「これは……あとでハウレもたくさん褒めてあげなきゃ。」
はしゃぐカイとハウとは対照的に、タスカル団は最初かなり遠慮していた。が、ライチュウの体毛みたいにつややかなパイの色と、美味そうな匂いには勝てなかったのだろう。やがてラップがおずおずと手を付けた。先っぽをちょっとかじり、2口目でフィリングに届いたところで、目が輝く。
「う、うまいっス! タッパも食ってみて!」
相棒に勧められタッパはしぶしぶパイを口に運んだが、瞬間、表情が変わった。ラップのように感激の声は上げなかったものの、急いで食べ進める様子からお気に召したことは明らかだ。
そんなタッパを、イーブイがきらきらした目で見つめていた。タッパは最初「なんだよ」と引きぎみだったが、やがてその視線がパイに向いているのに気づく。
「欲しいならハウからもらえよ。」
「きゅー。」
「……これがいいって? どれでも同じだろうが……。」
ぶつぶつ言いながらも、タッパは自分の食べかけをイーブイに渡した。イーブイは満足そうにるるんと鳴いてパイにかじりついた。
「ありがとー、タッパ。」
ハウはにこにこしながら、空になったタッパの皿におかわりの1切れを乗せた。タッパは何も答えなかったが、たいした間を置かずそれに口を付けた。
「なんで、ハウが謝ったんでスカ?」
甘くとろける昼食をしばらくみんなで楽しんだ後、ラップが尋ねた。さっきのバトルの件だ。意地をかけたポケモン勝負、負けたほうが謝るという話だったのに、結局勝ったハウも謝罪した。それがラップの腑に落ちなかったのだろう。
ハウは「うーん」と腕組みしてうなり、
「グズマさんの代わりがいるみたいな言い方しちゃったの、おれのほうこそすげーひどかったなって思うし、それに……」
うつむいたまま、ぽつりと続けた。
「おれは、うそをついていたからさー。」
ラップはじっとハウを見つめ、タッパも視線を寄越し、ハウを待った。
ハウは顔を上げ、彼らにきちんと向き直った。
「おれ、アローラのこと好きだよ。本当の意味でアローラを去ることはないと思うし、誰かを置いて行くつもりもない。けど……それと同じくらいの気持ちで、もっといろんな人やポケモンに会ってみたい。」
満腹になったイーブイがハウの懐に飛びこんできて、額をすり付けて甘えた。ハウはその体毛に優しく指を滑らせた後、欲張りだっていうのはわかってるんだけど、と続けた。
「知りたいんだ。今はまだ名前も声も知らない、人やポケモンたちのこと。だからおれ、アローラの外に出てみたい。『ここにいる』なんてうそだ。……ごめん。」
そう言って頭を下げた。
けっ、と息を吐き捨てたのはタッパだった。
「なーにがうそだよ。おまえのそんな考え、バレバレだっつーの。」
「えっ、そうなのー?」
見透かされていたことにハウは本気で驚いたらしい。真ん丸になったハウの目が形を戻さないうちに、「だいたいなあ」とタッパはまくし立てた。
「おまえにグズマさんの代わりができるかよってのも確かに腹立ったけど、それよりなによりおまえがおれらに余計な遠慮してることのが、よっぽど腹立つんだって。アローラ出たいんだったら、勝手に出やがれよ。なんなんだよ。タスカル団はおまえの足枷か?」
そんなことない、と答えようとしたハウに、タッパはさらに言葉を重ねる。
「情けねーじゃん。おまえはいっつもおれらの面倒見てさ。スカル団を……ボスにさえ見限られた団を続けてても、何も言わねーどころか応援までしやがるしさ。おれらだってバカじゃねーよ。わかってるよ、いまだに白い目で見るやつもいるってことぐらい。おまえがそれ、かばってくれてることぐらい。なのにおれら……。」
タッパの唇は凍えたように震え、最後まで音を紡げなかった。そんな彼を見つめるハウのほうも、何も言えないままだった。
人間たちが急に黙ってしまったので、イーブイは不思議そうにきゅうと鳴いた。その声の温度に勇気を得て、ラップが横からようよう口を開く。
「おれら、ずっと気にしてたんっスよ。きっとハウに迷惑かけてるんだろうなって。特にタッパが。」
余計なこと言うな! とタッパが慌ててささやいた。彼の唇は動きを取り戻せたようだ。
「と、とにかくだ。おまえがアローラの外を見たいなら、どこでも行っちまえってんだ。どうせカイと一緒なんだろ。」
ハウはタッパとラップの顔をしばらく見つめた後、少しはにかんで「うん」と答えた。崖下でのやりとりを思い出してちょっと頬を染めながら、カイも共にうなずいた。
仲の良い2人に、タッパは「あーもう、ムカつく! さっさと出てけ!」といつも通りの悪態をつく。ラップは安心したように笑い、イーブイも嬉しそうにきゅうきゅう鳴いた。
「もし旅先でグズマさんに会ったら、よろしく伝えてほしいっス。おれら待ってるっスカら、って。」
ラップの依頼に、カイは「えっ」と眉を上げる。
「グズマさん、他の地方にいるの?」
「たぶん。あの日グズマさん……おれらにだけ手紙を残してくれてて。」
ハウがうなずいた。すでに知っていたようだ。
タスカル団の表情に誇らしげな色が差す。
「『オレさまはアローラを出る。おまえらも好きにやりやがれ』ってな。さっすがグズマさん、スカしてるぜ!」
「ほんとにそれだけの短い内容だったから、どこに行ったのかまでは分かんないっスけどね。でもなんか偶然とか、奇跡とか、あるかもしれないじゃないでスカ。」
カイはにこりとうなずいた。
「うん、わかったよラップくん、タッパくん。グズマさんに会えたら、タスカル団がリリィタウンで待ってるって、伝える。」
「なあなあ、おれたちのことも待っててくれるー?」
冗談めいたハウの問いかけに、「けっ」と大げさに息をついたのはタッパだった。
「おまえらのことなんか知らねー。」
そうしてタッパはそっぽを向いて、トロピカルナッツパイをやたら大口を開けてほおばり、自ら次の句を継げないようにした。そうしなければきっと、突き放すような言葉の裏に秘めた「いってらっしゃい」がバレてしまうと思ったのだろう。
素直じゃないタッパの言動に、カイたちは顔を見合わせてこっそり笑った。
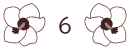 タスカル団たちは結局、トロピカルナッツパイを全部たいらげた。それから「おーし、タフにやってやるぜ!」などと高らかに吠えながら、修行に戻った。なんだか吹っ切れた様子だ。
タスカル団たちは結局、トロピカルナッツパイを全部たいらげた。それから「おーし、タフにやってやるぜ!」などと高らかに吠えながら、修行に戻った。なんだか吹っ切れた様子だ。
カイとハウは玄関先まで彼らを見送った。
すると、タスカル団と入れ替りで、ハラが帰ってくるのが見えた。
「あっ、じーちゃん、おかえりー! もうー大変だったんだよー!」
ハウは帰宅したハラにさっそく今までのことを報告する。ウルトラホールからビーストが現れたこと。カプ・コケコとカイたちの助力により無事に退けたこと。遺跡へのつり橋が壊れてしまったこと。ただし事前の打ち合わせ通り、2人が谷底に落ちたことは秘密にしておいた。
「なんと……1度ならず2度までも、客人のもてなしを任せてしまうとは。2人には頭が上がりませぬな。カプにも丁重に御礼を捧げに参らねば。」
そもそも先日のウルトラホールの出現があったからこそ、ハラはポニ島への出向を決めたらしい。
「ご存知の通り、異界からの来訪者の対処はしまキング・しまクイーンの責務の1つです。しかしその予見は容易なことではなく、長い年月をかけて積み重ねた経験や勘に基づく、わずかな傾向が口伝されているのみ。若きクイーンであるハプウにはまだ荷の勝つことと思い、補佐を行っておりました。しかしその間にメレメレ島への侵入を許してしまうとは……完全にわしの判断ミスです。」
「で、でもー。予想は難しいんでしょー? だったらじーちゃんのせいじゃないよー。」
ハウのフォローに、ハラはにこりと微笑む。
「心優しく頼もしい孫がいて、わしは大変幸いだったというわけですな。そしてその素晴らしい伴侶の存在も。」
不意の誉め言葉に、カイは「いやあの私はそんな」などという音をもごもごと口の中で転がした。結局ハウに助けられたことや、そのためにハウを危険な目に遭わせてしまったことが、かえってひどく申し訳なくなったからだ。
ハウはカイの赤らんだ顔を横から眺めて楽しんだ後、「もうひとつじーちゃんに話したいことがあってー」と切りだした。
「おれ、アローラを出て、世界中を旅したいと思ってるんだ。カイと一緒に。」
普段は細いハラの目が、ぴくりと開いて2人を見た。
カイもハウに続く。
「私たち、もっとたくさんの人やポケモンに会いたいと願っています。島巡りの時のように……ううん。きっとそれ以上に。」
「言うなれば、世界巡りって感じ? ……どうかなー、じーちゃん?」
ハラは腕組みをして「うーむ」とうなった。カイとハウは緊張して、ハラが次に発する言葉を待ち構える。
だがハラは存外時間をかけず、表情をやわらかく崩した。
「わしに何の許可を取ることもありますまい。すでにハウの心は決まっているのでしょう。ならばその通りに行動するべきです。」
じーちゃん! とハウはハラに抱きついた。ハラも固い抱擁を返し、「しっかり世界を見るのですぞ」と激励の言葉を贈った。
「カイ。我が孫をよろしくお願いいたします。」
「はい。こちらこそ、です。」
「じーちゃん、おれ、カイがいればどこだって平気だよ! なんたってカイはおれの、素晴らしいハンリョだもんねー。」
再び頬を染めて「それにポケモンたちだっているから」と付け加えるカイ。その照れ顔を愛でながら、にこにこうなずくハウ。ハラはそんな若い2人を、微笑ましく見つめていた。
「ハウ、カイ。世界のどこにいても、忘れなさるな。昼間は太陽が、夜には月が、アローラと変わらぬ光できみたちを見守っていることを。」
その言葉は2人の心に、いつまでも消えない明かりを灯してくれた。
カイとハウは共にハラに向き直ると、「はい!」と元気よく答えた。
ハウがカイを家まで送ると申し出てくれたので、カイはお言葉に甘えることにした。もちろん、そうすればそれだけハウと一緒にいられる時間が長くなるからだ。
「カイのかーちゃん、世界巡りのお許しくれるかなー。」
1番道路を歩きながら、ハウが問う。
大丈夫だと思うよ、とカイは軽い調子で答えた。
「引っ越し先でいきなり島巡りに行くって言っても、平然と見送ってくれるぐらいだし。」
「あははー、それもそうだねー。じゃあ後、きちんと話さなきゃならないのは……」
「ククイ博士、だね。」
そこでカイがうつむいたので、ハウはその顔をのぞきこんだ。
「博士のことだから、きっと快く送り出してくれるよー。」
「そうだね。でもだからこそ……心苦しい。」
「どうしてー?」
「アローラリーグを造るのはククイ博士の夢だったでしょ。私のわがままで、それを潰すことになるんじゃないかって。」
ハウはカイを見つめたまま、優しいなーカイは、とつぶやいた。
「だけど初代アローラリーグチャンピオンさん、ひとつ勘違いしてるよー。それはきみのわがままじゃない。」
どういう意味? と問う視線をカイが向けると、ハウはにっと笑った。
「おれときみの、わがままだ。」
それはカイがアローラに来て、空ではない場所で見つけた太陽の色だった。その温かな光に誘われてカイも微笑み、うなずく。
とにもかくにも、まずは相談してみなければ始まらない。カイとハウは共にククイを訪ねる約束を交わし、その日はさよならを告げた。
数日後。
カイとハウはククイの研究所を訪れ、イワンコやブルーなど研究所のポケモンたちとじゃれあっていた。扉を開けたらあっという間に飛びつかれてしまったのだ。ここの子たちはいつも元気いっぱいだ。きっとこれくらいのほうが、技の研究者にとってはちょうどいいのだろう。
ひっくり返ったハウの腹にイワンコが乗り、「わんわん!」と誇らしげに吠えたところで、ククイがお茶と菓子を持ってきた。
「はは、2人ともポケモンたちの相手をしてくれてありがとう。そろそろバトルごっこは封印して、ティータイムにしないかい?」
「するー!」
勢いよく起き上がったハウからイワンコがころんと落ち、くぅんと鼻を鳴らす。けれどククイがポケモンフーズも用意してくれていたので、イワンコはすぐに機嫌を取り戻した。
乱れた髪や身だしなみを整えて、カイとハウはようやくソファに腰を落ち着ける。今日の茶請けはヨウカンだった。ククイの妻バーネットの、最近のお気に入りらしい。先日カフェで食べたシンオウ銘柄のが特に美味しかったそうだとか、カイの故郷ジョウトではメジャーな菓子であるとか、しばらく雑談とお茶を楽しんだ後、「さて」とククイが切りだした。
「それで、2人が話したいことというのは、何かな?」
カイとハウはそろって居住まいを正し、ククイに向き直る。
「おれたち、アローラを出ようと思ってるんだー。」
島巡りでさまざまな人やポケモンと出会ったように、世界を巡って、もっとたくさんの出会いを経験したい。他の地方の景色を自分の目で見て、その空気を肌で感じたい。
一生懸命に思いを伝えるカイとハウの望みを聞いた時、ククイはさほど驚かなかった。それどころか、嬉しそうな様子さえあった。
「きみたちなら、きっといつかそう言うと思っていたよ。ぼくの未来予知は大当たりだ。」
しかしククイの賛同を得ても、カイは表情を曇らせたままだった。
「もしかして、空元気に見えてるのかな?」
ククイに図星を突かれ、カイはさらに言葉を詰まらせてしまう。
「あ、あのー! カイは自分がリーグを離れることで、せっかくククイ博士が叶えた夢を壊しちゃうんじゃないかって、不安に思ってるんだよー。」
ハウが助け舟を出してくれた。
そうなのかい、とククイが尋ねるので、カイはうなずいた。
「そうか……。ありがとう、カイ。だけど心配には及ばないよ。きみがいない間、アローラリーグチャンピオンの座はしっかりと守ってみせるさ。」
カイとハウはきょとんとしてククイの顔を見た。
「……誰が?」
「もちろん、このぼくだぜ!」
ククイの親指が、びしっと自身の胸を突いていた。
ええっとカイは思わず声を上げる。
「ククイ博士が!? で、でも……いいんですか?」
「言っただろう、ぼくの未来予知は大当たりだって。四天王にはもう話をつけてある。望む相手には、チャンピオンに足る実力があることも示してみせた。ああ、もちろんきみが納得できないなら、きちんと正式戦を終えてからにしよう。ぼくのポケモンたち、前回のバトルからさらに技を磨いたんだぜ。」
「いやそういう意味ではなく……。だって博士、自分で造ったリーグのチャンピオンになるつもりはないって言ってませんでした? それに忙しいでしょう? リーグの運営だけじゃなくて、研究もあるし、」
ロイヤルマスクの活動もあるし、というのは危ういところで飲みこんだ。
大丈夫さ、とククイは褐色の肌に映える白い歯を見せて答える。
「確かにリーグ設立直後は大忙しだったが、今はスタッフも慣れてきたし、ずいぶん落ち着いた。チャンピオンになるつもりも、初めはなかったが……きみたちのポケモンが頂点で輝く技を繰り出すのを見て、なんだかうずうずしてきてしまってね。」
ククイの目には、アローラリーグ頂点のバトルフィールドに舞う風や炎の色が、鮮明に映っていた。
「それにぼくのガオガエンも同じ気持ちみたいでさ。トレーナーとしてポケモンの思いを無下にするわけにはいかない。カイがアローラを離れている間くらいなら、チャンピオンの椅子に座ってみてもいいかなと、今は考えている。」
それからククイは少し改まって、なあカイ、と呼んだ。
「きみがチャンピオンになった時……アローラの人もポケモンも最高だ、ってぼくが言ったの覚えてるかな。それを世界に知ってほしいという夢が叶ったと。その気持ちは今も変わらない。でも同時に、それだけじゃないとも思っている。」
ククイはカイとハウの目を順番にのぞきこんだ。
「アローラの外に出てこそ、伝えられることもある。アローラの外に出てこそ、見えるものもある。つまりカイがリーグから離れることは、ぼくの夢を壊すどころか、違う方向からの手助けになるってわけさ! きみたちにはぜひ旅先で、アローラの魅力を広め、他の地方の素晴らしさを知ってほしいんだ。きみたちにしかできないやり方で。」
「私たちにしか……」
「できないやり方……。」
カイとハウは互いの顔を見つめた。言葉にせずとも、このパートナーとなら臨める景色があることを、両者ともすでに理解していた。
ハウの隣なら。
カイが一緒なら。
「アローラのことは心配いらない。行っておいで、2人で。そこにまだ見ぬポケモンがいるのなら、迷わずどこへだってウルトラダッシュアタック! だろ?」
ククイに相談を始めてからずっと陰ったままだったカイの表情が、ようやく晴れた。カイはもう一度ハウと目を合わせると、共にククイに向き直り、
「はい!!」
2人同時に元気よく口を開いた。
カイとハウの出立準備はとんとん拍子に進んだ。
メレメレ島に連続で生じたウルトラホールについて、ビッケからの続報もあった。2回におよぶウツロイドの世界との接続は、国際警察の件とは無関係の単発的なものだったらしい。今のところ新たな裂け目の兆候は皆無だそうだ。
「ホールの発生については、国際警察の件も含め、いずれグラジオ様にもお話しようと考えています。今はまだそれどころではありませんけれど。そうすれば今後、万が一ホールが開いたとしても、タイプ:フル……いえ、シルヴァディがビースト対応の強力な味方になってくれるでしょう。だからカイさん、ウルトラホールのことはどうかご心配をなさらずに。この件はエーテル財団が必ず後始末を付けますから。」
グラジオとシルヴァディがいてくれるなら心強い。カイは重ねてビッケにお礼を言い、安心して荷造りに戻った。
その後、ククイに相談をした日からしばらくを経て、カイとハウはハウオリシティの空港にいた。最初の目的地に選んだのは、イッシュ地方だ。
みんなに見送られ、留守番をするポケモンたちの世話をよろしく頼み、カイとハウは出発ゲートをくぐって飛行機に乗りこんだ。
滑走路の上でゆっくりとゆられている間、2人はあまり言葉を交わさなかった。さまざまな色に輝く光は、全部混ざると真っ白になるものだ。
いよいよ機体の速度が上がっていく。きっともうケンタロスライドよりもスピードが出ている。轟音が響き、ぐんと押し潰されるような浮遊感と共に、カイたちは空へ舞いあがった。
歩き慣れたアローラから離れ、目指す土地をまだ踏んでいないこの時間、カイとハウは自分たちがどこにも属していないような不思議な心地を覚えた。たったひとつ確かなのは、カイの隣にハウがいて、ハウの側にはカイがいるということ。
カイ、と名前を呼んで、ハウはそっとささやいた。
「おれは、きみの隣にいてもいいですか。」
どうしたのあらたまって、とカイはくすくす笑い、ハウの手に自分の手を優しく重ねた。
「はい。誰より近い特等席にいてください。いつも、いつまでも。」
そうしてカイとハウは互いを見やり、微笑んだ。
はてしない物語の予感が、2人の未来を温かく包んでいた。
「第2幕 ハウとカイの世界巡り」につづく!
