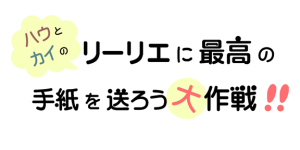9. クチナシの写真
1 2 3
薄い霧の中に、深紅の花が咲いていた。しっとりとした細やかな滴が頬に当たって涼しい。赤の中に潜んでいるのだろうポケモンたちの澄んださえずりが、時々空気を震わせた。
ここはウラウラ島の西にある湿原、ウラウラの花園。この花園を抜けた先、十七番道路に、クチナシが常駐するポー交番があった。リーリエに送る写真を撮るためにクチナシの元を訪れる道中、カイとハウは咲き乱れる真っ赤な花を眺めながら、木道をのんびりと歩いていた。ロトム図鑑も二人の上空を飛んで、楽しそうに写真を撮ったり図鑑のデータを更新したりしている。
「島巡りでここを通った時は、観光どころじゃなかったもんねー。」
赤花の周りをひらひらと戯れるアブリーたちに手を差しのべながら、ハウがしみじみ言った。あの時はスカル団にさらわれたヤングースを助ける途中で大変だった。カイはハウに同意して感慨深くうなずくと、今は十分に穏やかな心持ちで、花園の甘い空気を胸いっぱいに吸いこんだ。
「カイー! 見て見て、あそこにオドリドリが群れてるー!」
ハウが指差した先には、花園と同じ色の真っ赤な羽毛に身を包んだオドリドリが四羽、ちょんちょんと辺りの花弁をつつきまわっていた。
「どうやら食事中みたいロト。オドリドリは花の蜜が大好きで、蜜の種類によって姿を変えるんだロ。」
いつの間にかロトム図鑑が降りてきて、解説してくれた。へーと感心の声を上げるハウ。
「可愛いねー。メレメレ島の黄色もいいけど、こっちの赤色もきれいだなー。」
ハウがカイの耳元でささやく。そうだね、とカイもささやきを返した。
二人が静かにしていたからか、オドリドリたちは目の前の蜜に夢中で逃げようとしなかった。それでカイとハウは、オドリドリの緋色の体の上で白い飾り羽がぴょこぴょこ動くのや、くちばしで花の蜜を器用になめ取るのや、黒く縁取られた羽の先が四羽分つながり重なって独特の紋様を描くのを、面白く眺めた。ロトムも何枚か写真を撮ったようだ。
するとやって来たのは、一匹のアブリボン。食事中のオドリドリたちに近づいてなにやら話しかけ始めた。手には赤い団子を持っている。しばらく四羽と一匹の交渉が続いた後、オドリドリたちがそろって高く鳴き、一斉に翼を広げたかと思うと一列に並んで距離をとった。
始まったのは、オドリドリたちのダンスだった。
めらめら舞い散る炎にも見える踊りは、感情すべてを燃料にしているかのように情熱的で激しかった。高いさえずり、目にも留まらぬ速さのステップ。それを四羽同時に一糸乱れぬ動きで繰り出すのだから、その鮮やかさといったら花園の花でさえ見劣りしてしまうほどだ。
 いつの間にか最初のアブリボンの隣に別のアブリボンが一匹寄り添って、一緒にダンスを観覧していた。他にも何匹かのアブリーと、いろんな草ポケモンや虫ポケモンたちも集まっている。ついでにカイたちのように遠巻きに見守る人間たちも集まって、オドリドリたちは極上のステージに様変わりした花園の中心で見事なフィニッシュを決めた。
いつの間にか最初のアブリボンの隣に別のアブリボンが一匹寄り添って、一緒にダンスを観覧していた。他にも何匹かのアブリーと、いろんな草ポケモンや虫ポケモンたちも集まっている。ついでにカイたちのように遠巻きに見守る人間たちも集まって、オドリドリたちは極上のステージに様変わりした花園の中心で見事なフィニッシュを決めた。
「うわーっ、とっても素敵!」
向こうの木道から眺めていたダンサーが、思わず称賛の拍手を送った。するとオドリドリたちは驚き、慌てて四方に散らばった。そのくちばしには各々アブリボンから褒賞としてもらった赤い団子がはさまっていた。他のポケモンたちもそそくさと赤花の中に去っていき、花園にはまた静かで穏やかな時間が流れ始めた。
「面白いもの見られたねー。」
「ボク、見とれちゃって、あんまり写真撮れなかったロト……。」
「そのほうがいいよ、ロトムー。写真もいいけどさー、自分の目で見て感じるのって、すっげー価値があることだよー。」
ハウの言葉に、ロトムは気を取り直した。
花園に一歩入った時から、ハウは機嫌が良い。景色はきれいだし、ポケモンもたくさん見られるし、ウラウラの花園をかなり気に入ったみたいだった。その上珍しいオドリドリのダンスまで目にすることができたから、ハウはすっかりご満悦だ。もう次の場所を指し「カイー!」と呼んでいた。
「あの霧の向こうにも影が見えるよ。何のポケモンだろうねー!」
待ちきれずに、歩みは自然と速くなる。ところが、霧に隠れたそれらの輪郭がはっきりと見えた時、木道を高く踏み鳴らすカイとハウの足音は突然停止した。
それは、二人の人間だった。
白いニットキャップは二か所が黒く塗りつぶされ、落ちくぼんだ眼窩がんかのようだ。黒いバンダナで口元を隠し、タンクトップもハーフパンツも黒。その真っ黒な胸元で、どくろを模した大ぶりのペンダントが鈍い銀色に光っている。二人とも全く同じ出で立ちだった。
「スカル団……。」
ハウが一歩足を下げ、モンスターボールに手を近づけた。
カイはロトム図鑑を鞄の中にしまいこんだ。
スカル団の男たちは、カイとハウをにらみつけていた。
「ヨーヨー。ユーたち、何のつもりでスカ?」
男の一人が、刺々しい口調で問う。それはこっちのセリフだとカイが言い返す前に、さらにもう一人が口を開いた。
「まるで島巡りトレーナーみたいにきゃあきゃあはしゃいで、まさか二周目の島巡りとかやってるつもりか? 自分らは大大試練まで達成できたからって、いい気になってよ。一周の島巡りもできなかったおれらに当てつけるために?」
「違う! そんなわけないよー!」
ハウが叫んだが、彼らは聞く耳を持たなかった。
「口ではなんとでも言えるよな。」
言葉のとげをさらに鋭く研いで、彼らはモンスターボールを手に持つ。
「おまえらの行動それ自体が、最高に最低でムカつくんだよ。いいからぶっ壊されろよ!」
有無を言わさず、二個のボールが宙を舞った。
ポケモンバトル。ハウは途中までボールに近づけていた手で素早く応じ、カイもハウに続いてジュナイパーを繰り出した。
カイのジュナイパー、ハウのアシレーヌに対して木道の上に現れたのは、ズバットとスリープ。島巡りを諦めた者たちの、まだ進化もしていない小さなポケモンだった。
「やるッスよズバット、かみつく攻撃!」
「スリープは念力だ!」
あまりにもレベルが違いすぎると、カイにはすぐ分かった。けれどもトレーナーの指示を聞いて、果敢に技を出そうとするポケモンたちにとっては、善も悪も手段も目的も関係なかった。ただパートナーと共に撃破するべき目標だけを捉えていた。そのひたむきさに手加減とか同情とかで答えるのは、ポケモンバトルとして失礼なことだった。
カイの眼に宿った光は、そのままジュナイパーの力となる。
「マルク、影縫い!」
「アシレーヌ、ムーンフォースで迎撃!」
黒い影をまとったジュナイパーの矢羽が、一寸の迷いもなくズバットを撃ち抜いた。次いでアシレーヌが放ったまばゆい月光が、念動波をあっさりと吹き飛ばしてスリープを焼く。
スカル団の小さなポケモンたちは、すっかり戦う気力を失って木道にひっくり返った。
「なっ、なんなんスカ! 瞬殺じゃないでスカ!」
「ちっくしょう、覚えてやがれよ!」
スカル団員たちは大慌てで倒れたポケモンたちをボールへ戻すと、どたどたと霧の中を駆け去っていった。追うことはなかった。カイもハウもその場に立ったまま、彼らの背中を見送った。
「お疲れ様、マルク。ありがとう。」
カイがジュナイパーをボールに収納する。ハウも黙ってアシレーヌを光に包んだ。いつものハウなら労いの一言でもかけてやるのに。
「ハウ……大丈夫?」
のぞきこんだハウの顔は、スカル団が消えた一点を苦々しく見つめていた。眉間にしわが寄り、口をぎゅっと一文字に結んでいる。
が、ハウはカイの声かけに気がつくと、すぐにその表情を隠してこちらを向き、笑顔を作った。
「うん、大丈夫ー。早くクチナシさんに会いに行こう。写真と寄せ書き、ゲットしないとねー!」
やたらと明るい声だった。いつもの口調に聞こえるように、自分で自分をだますための音だった。何と返事をすればいいか、カイが思いあぐねていると、
「誰に会いに行くって?」
背後から声をかけられた。驚いてカイとハウが振り返ると、薄霧の先、十七番道路とは逆の方向から、警官服を来た猫背の中年男が現れた。ウラウラ島のしまキング、クチナシだった。
 「コーヒー飲むか?」
「コーヒー飲むか?」
ポー交番に着いた後、クチナシはカイとハウをソファに並んで座らせ、そう尋ねた。二人のために渋々場所を空けてくれたニャースたちが、ちょっと不機嫌そうにごろごろ鳴いている。
ニャースたちを気にしつつも、飲みます、と答える二人。しばらくすると、黒い液体が耐熱の紙カップに注がれて出てきた。
「ありがとうございます。」
砂糖とミルクをたっぷりと入れ、ハウは早速コーヒーを頂く。直後、あちっと小さくのけぞった。カイはちょっと微笑むと、ふぅとひと吹きして熱を冷ましてからカップに口を付けた。カフェのグランブルマウンテンほど気取らない、素朴なインスタントコーヒーの味は、優しく体に染みいった。
ウラウラの花園で合流したクチナシは最初、島巡りでもないのにこんな場所にやって来た客人をいぶかしんだ。しかしリーリエに手紙を送るためアローラの各地を訪ねているという事情を説明するとあっさり納得して、「もうすぐ日も暮れるし、こんな所で立ち話もなんだから」ということで交番まで連れ立ってくれた。クチナシ自身は「パトロール中」だったらしい(その詳細な中身については、カイもハウも深入りしなかったが)。二人のことも、スカル団とポケモンバトルを始めた辺りから見ていたようだった。
「大変だったな。スカル団のやつらに絡まれてよ。」
クチナシは自分のコーヒーを片手に、二人の向かいのソファに腰かけた。せっかく居場所を追われた先で落ち着いていたのに、再び避ける羽目になったニャースが二言三言抗議していたが、クチナシがぽんぽんと頭を撫でてやると大人しくなった。
「見てたなら止めてくれても良かったのにー。警官でしょー。」
「だってあんちゃんら強くて、止める間もなくバトル終わっちまったんだもん。」
「スカル団は、まだこの辺りに多いんですか。」
カイが尋ねると、クチナシは真っ黒なコーヒーを一口すすって、まあな、と答えた。
「ポータウンにはうじゃうじゃ残ってる。ポータウンだけじゃない。アローラのどの島でも、リーダーを失ったしたっぱどもが、明日も分からずうろついてるみたいだな。」
そうですか……とカイはつぶやいた。
ウルトラスペースから戻ったスカル団ボスのグズマは、その後、団から姿を消したらしい。なんとなく風のうわさで聞いていたことだった。
「やつらを見かけても、関わらないほうがいいぜ。」
クチナシの忠告に、「でも」とハウは口を開いた。開いて、それきりだった。何がどう「でも」なのか、ハウ自身整理がついていないのだろう。クチナシは小さくため息をついて、うなだれるハウを眺めた。
「あんちゃんらは、もう十分巻き込まれただろうが。」
それはたぶん、島巡りで遭った一連の事件のことも指していた。
ハウは答えられないままだった。
にゃーお、とニャースのあくびが一つ、部屋に響いた。
スカル団員たちと出会ってからずっとカイの鞄の中に引っこんでいたロトムが、そっと顔をのぞかせて様子をうかがっていた。
「あ、そうだクチナシさん。写真撮らせてください。」
重くなった空気をはらうようにカイが言った。それでロトム図鑑は、ようやく自分が出ても大丈夫そうだと、ぴょこっと鞄から飛びだした。
「そうそう、写真ー。あと寄せ書きも!」
ハウも顔を上げた。
クチナシはああ、とうなずいた後、ちょっと頭をかいた。
「こんなおじさんの写真やらメッセージやらもらったって、別に嬉しくもなんともないと思うけどねえ。」
「嬉しいかどうかはリーリエが決めることだからー。」
そう言ってハウはクチナシに寄せ書きの紙とペンを渡す。クチナシはまだ渋々といった様子だったが、ざっと他の人の文面を眺めた後、紙の上にペン先を走らせ始めた。
その間にカイとハウは、写真の構図を考える。
「なー、この辺から撮ればいいんじゃない?」
ハウがソファから立ち上がって、カイとロトム図鑑を手招いた。レンズを向けて構えると、ちょうどソファに座っているクチナシの全身が画面の中に収まる距離だった。
「うん、いい感じ。」
「ばっちりロト!」
そこでクチナシが寄せ書きを書き終えたので、カイはクチナシにニャースを抱えてほしいとリクエストする。返してもらったペンと寄せ書きを受け取ったハウも、それナイスアイデア! と賛同した。子供二人に囲まれてしまっては、さすがのしまキングも成す術がない。はいはい、と苦笑しながら隣のニャースをひざの上に乗せた。
「クチナシさん、もう少し笑って。」
「笑ってー。」
「悪いね。人相が良くないのは生まれつきなんだよ。」
なんて皮肉を飛ばされながらも、シャッター音は軽快に鳴った。
「うーん、結構いい感じに撮れたと思うんだけど、どう?」
何枚か撮影してから、カイはハウに写真を見せて意見を求める。画面に表示されているクチナシの笑みは、やっぱりちょっとぎこちない気がしたが、クチナシらしいと言えばクチナシらしいかもしれない。抱えているニャースはとても可愛い。
「うん。いいと思うよー。」
ハウの返事も及第点だったので、カイは撮影を切り上げることにした。
「ありがとうございました、クチナシさん。いい写真が撮れました。」
「はいよ。お疲れさん。」
「寄せ書きと写真お願いして、コーヒーまでおごってもらっちゃってー、これは何かお礼をしなくっちゃねー。」
「いいっていいって。コーヒーはついでだし、そんな気ぃ遣わなくても……いや、待てよ。」
はた、とクチナシが手をあごに当てた。
「そんなら一つ頼まれてもらうかな。」
 カイの握る細い棒の先で、チラーミィのしっぽみたいな毛束が揺れている。みょんみょんと絶妙なリズムで踊るそれに、一匹のニャースが勢いよく飛びついた。カイはさっと棒を動かして避ける。すると別のニャースが「なふぅっ」と興奮した声を上げながら、毛束にねこパンチを繰り出した。逃げるように棒を小刻みに振ると、ニャースたちはますます毛束に夢中になって、にゃんにゃん鳴きながらカイの周りを跳ねまわった。
カイの握る細い棒の先で、チラーミィのしっぽみたいな毛束が揺れている。みょんみょんと絶妙なリズムで踊るそれに、一匹のニャースが勢いよく飛びついた。カイはさっと棒を動かして避ける。すると別のニャースが「なふぅっ」と興奮した声を上げながら、毛束にねこパンチを繰り出した。逃げるように棒を小刻みに振ると、ニャースたちはますます毛束に夢中になって、にゃんにゃん鳴きながらカイの周りを跳ねまわった。
「わーカイ、ポケじゃらしの使い方、上達したねー。」
ソファの上で寝そべるニャースをブラッシングしながら、ハウが笑った。
ニャースたちの遊び相手をしてほしい、というのがクチナシの頼みだった。それくらいならお安いご用です、と承諾したカイとハウに、クチナシはニャース用のおもちゃや毛づくろい道具を渡した後、「じゃよろしく」と言って出かけてしまった。
 ポー交番にはもうかなりの時間、カイとハウとニャースたちの声だけが響いていた。ロトムは部屋の隅ですやすやとお休み中――図鑑の充電中だった。
ポー交番にはもうかなりの時間、カイとハウとニャースたちの声だけが響いていた。ロトムは部屋の隅ですやすやとお休み中――図鑑の充電中だった。
「クチナシさんどこ行ったんだろうー? けっこう経ったよねー。」
ハウが言った時だった。交番のドアが開いて、クチナシが戻ってきた。ニャースたちが次々に鳴いて出迎える。その顔を一つずつ見て、クチナシは目尻のしわを深くした。
「おっ、ニャースたち満足そうだな。」
そしてカイとハウに「遊んでくれてありがとよ」と感謝を述べながら、カウンターの上に持っていた袋をどさりと置いた。
「こいつは礼だ。晩飯。食ってくだろ?」
カイもハウも、ちょっと目を丸くして、クチナシの顔とカウンターの袋を交互に見つめた。
「ニャースたちと遊ぶのは、手紙への協力とコーヒーのお礼じゃなかったのー?」
「あ? そうだっけか? おじさん年寄りだから忘れちまったなあ。」
ひょうひょうとのたまうしまキングに、素直に感謝すればいいのかさすがに遠慮するべきかカイとハウが決めかねているうちに、クチナシはニャースたちの晩飯を用意し始めた。ざらざらと勢いよく大皿に盛られるポケモンフーズに、ニャースたちがわーっと群がって押し合いへし合い。田舎の小さな交番は、にわかにハウオリショッピングモールのバーゲンタイムよろしく賑やかになった。その中で困惑の表情を浮かべてじっと動かない子供らを、クチナシは不思議そうな目で見る。
「ん、腹減ってないのかい。」
「いえ、そういうわけでは……。」
「じゃあ食いな。せっかく買ってきたんだから。いいポケ丼屋があってよ、最近お気に入りなんだ。」
カイとハウは顔を見合わせた。確かに、遠慮したところでクチナシは二人分の夕食の処理に困るだけだろう。特にどこかでディナーの予約をしているわけでもなかったし、二人はクチナシの厚意を受けることに決めた。
「ありがとうございます。」
「いただきます。」
クチナシは自身の分を取り出して二人に袋を渡すと、立ったまま食べ始めた。交番の主が立ち食いしているのに、自分たちだけソファに座っているのもどうかと思ったのだが、カウンターに寄りかかりニャースたちを眺めているクチナシの様子は、結構満足そうだ。カイはあまり心配しすぎないことにして、受け取った容器のふたを開けた。
一口サイズに切った魚介を、香味野菜や海藻、濃厚な口当たりのきのみ、ヤドンのしっぽの水煮などと共にあえ、白飯に盛りつけたのがポケ丼だ。ポケモンも大好きな味だからとか、ヤドンを使う「ポケモン丼」の略とか、アローラの古い言葉に由来するとか、ネーミングには諸説ある。観光客にも人気の、アローラのロコフードだ。
「わー、美味しそう!」
だからハウもきっと初めて見る料理ではないだろうが、見た目はとても気に入ったようだ。早速「いただきます!」と手を合わせ、スプーンを手に持っていた。
「この店、下味にこだわっててよ。樹上で熟したリンドの実を発酵させて作ったソースを使ってるんだと。ポニ島産のやつだけを使うのが肝らしい。」
「へーおうなんだー。すごうおいいいでう!」
半分ぐらい言葉も食べてしまいながら、ハウは実感を込めてもぐもぐうなずいた。カイも「いただきます」と手を付けた。
新鮮な魚の食感。漬けこんだ特製ソースの風味と塩加減が、魚の旨味をぐんと引き出している。絶妙な配分で混ぜられたきのみと野菜がさわやかに味を調えて、いとも簡単に二口目が誘われた。すると先とは異なる種類の魚がやってきて、違う歯ごたえと香りなのに同じ下味によってまとめられているから、全然けんかしない。手がどんどん進んでしまう。ほんのりとした甘味の中に深い旨味が隠れているのは、ヤドンのしっぽだろう。下味の付け方でこんなにも表情を変えるなんて、知らなかった。
「美味しいです、クチナシさん。」
思わず無言で数口食べてしまった後、はっとしてカイは感想を述べた。
「そうかい。そりゃ良かった。」
クチナシはこちらを見もせずに返事をしたが、それが彼なりの上々の答えだった。
そうして二人が夢中で頬張っていたポケ丼の中身も、ほとんど空に近づいた頃だ。
「あれ、クチナシさんはー?」
先に容器を空にしたハウが、ふと顔を上げて尋ねた。見渡すと、確かに交番の中にはたくさんのニャース以外、自分たちと、充電を終えてその辺を飛んでいるロトム図鑑しかいない。
「出かけたのかな?」
「もう夜なのにー?」
納得いかない様子のハウは、ごちそーさま! と言って立ちあがった。
「おれちょっと外見てくるよ。」
「あっ、待ってハウ、私も行く。」
カイも急いで食事を片付け、二人は交番の外へ出た。
「あー、ボクも置いていかないでほしいロトー!」
と、すっかりお目覚めのロトム図鑑も付いてきた。
ひやりとした空気が肌を撫でた。涼しい。日はすっかり暮れ、ラッタとかアリアドスとか夜行性のポケモンの鳴き声がちらほらと聞こえる。
向こうの方にぽつんと立った街灯が寂しく道を照らしていた。その街灯の光も絶えた暗い道路の端に、クチナシはいた。無造作に置かれた木製コンテナをベンチにして、ペルシアンと二人、空を眺めていた。
今夜は満月だった。
カイとハウはクチナシがすぐに見つかったことにほっとして、彼らに近づいた。
「月が綺麗ですね。」
カイが声をかけると、クチナシは二人の方に視線を下げて薄く笑った。
「そういうのはもっといい人に言うもんだぜ、カイ。」
「お月見してたのー?」
「ああ。こいつが満月見るの好きでよ。」
ペルシアンの満月みたいな丸い頭に、クチナシの骨ばった手が乗った。クチナシの手が左右に揺れると、ペルシアンは心地よさそうに喉をごろごろ言わせた。月光はペルシアンの毛皮によく映え、まぶしすぎない明るさはかえってクチナシの心根をくまなく照らす。二人ともとてもリラックスして見えた。いい画だとカイは思った。
「……あ。」
カイはロトム図鑑が自分の後ろにいることを確認する。それからクチナシに尋ねた。
「写真、撮ってもいいですか?」
隣でハウがカイの意図を理解した。当のクチナシは最初、問いの意味が分からなかったようだ。
「月はおれのもんじゃねえから、ご自由にどうぞ。」
「クチナシさんとペルシアンを撮りたいんですよ。」
くすくすカイが笑い、ロトムはもうカメラモードの準備万端だった。クチナシは少し困った顔をする。
「さっき撮ったじゃねえか。」
「念のためです。特に笑顔とか作らなくていいんで、ペルシアンとお月見を続けてください。」
「参ったねえ……。」
頭をかきながらも、自然体でいいならばと思ったのだろう。お月見続けてろってよ、とペルシアンに話しかけながら、クチナシは月の光に横顔を濡らした。
カイは画面の中にクチナシとペルシアン、そして満月が入っているのを確認して、シャッターボタンを押した。
撮れた写真をのぞき見て、ハウがにっこりうなずいた。
「オッケーです。ありがとうございました、クチナシさん。」
「へい。どうも。」
「ほら、さっきよりいい構図だと思いません? リーリエに送るの、こっちにしようかと思うんですけど。」
ロトム図鑑の画面を差しだすと、クチナシとペルシアンはしばらく画面を眺めていた。
「おじさんは写真のことは分かんねえからな。好きなほう使いなよ。」
そう言って図鑑を返すクチナシは、まんざらでもない雰囲気だった。ペルシアンもクチナシに続けて、低い鳴き声をやわらかく伸ばした。カイにペルシアンの言葉は分からないが、少なくとも敵意はない音だと思った。
静かな夜だった。風は穏やかで、空には雲一つない。雨の多いこの地域には珍しいことだった。満月に誘われて外に出てしまうのも無理はない。きらめく星々は紺布に宝石の粒を撒いたようで、その光景はきっと空と海が混じる水平線まで広がっているのが見えただろう。そびえ立つポータウンの外壁が、空を黒く切り取っていなければ。
ボスを失ってもなお多くのスカル団員たち――あるいは元スカル団員たちが中に残っているというその町は、今は闇に沈んで眠っていた。
ふとカイは、クチナシの赤い瞳が月の光ではなく町の影を映していることに気がついた。
「ポータウン、見てるんですか。」
カイの質問に、クチナシは否定も肯定も返さなかった。ただぽつりと小さな声でつぶやいた。
「壊れるのは一瞬なのになあ。変わるのは、時間がかかるんだよなあ。」
少しの間。
「でも、」
口を開いたのはハウだった。交番の中で続かなかったハウの言葉は、今、違う形で音になる。
「月が昨日と同じ形の日は、ないと思う。」
クチナシがハウを見た。それから、にやっと唇をゆがめた。
「若い子の感性はうらやましいねえ。」
そうしてカイたちはそのまましばらく、満月の下で共に時間を過ごした。